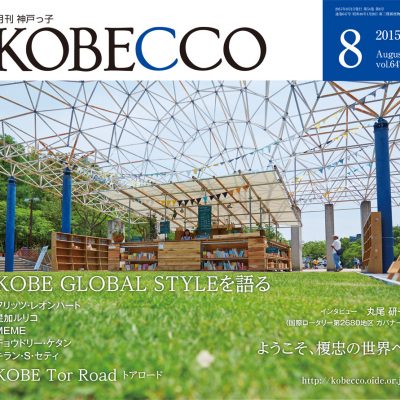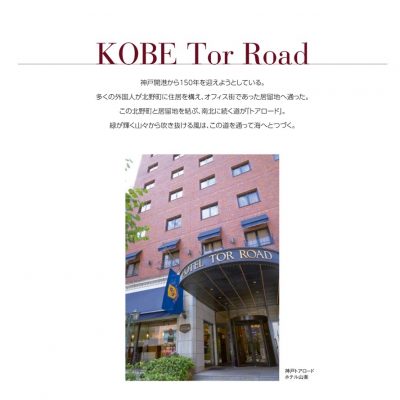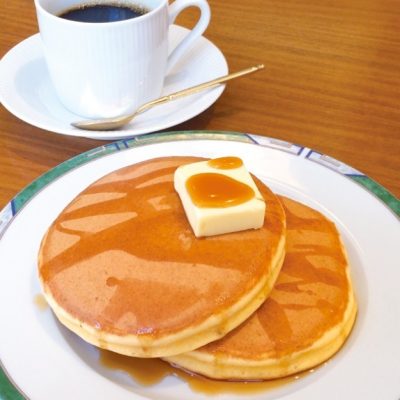8月号
神戸鉄人伝(こうべくろがねびとでん) 第68回
剪画・文
とみさわかよの
ファッション・デザイナー
石原 暁美(いしはら あけみ)さん
「その人のための服を作る」「顔の見えない服は作らない」と映画『繕い裁つ人』の主人公“南市江”。その市江とそっくりなデザイナーが実在します。「一から十まで自分で目を通しているから、思い通りのものが作れる」と芦屋のアトリエで自ら立体裁断をし、針を持つ石原暁美さん。「ファッション・デザイナーと言うと何だか華々しくて。私はクチュリエール、街の小さなクチュールでいいんです」と話す石原さんに、お話をうかがいました。
―この業界に入られたのは?
家の事情から「手に職を」との母の希望で、洋裁学校へ進みました。でも花嫁修業のお嬢さんばかりでのんびりムード、とても洋裁を職業にという雰囲気ではなくて。そこで西宮の洋裁店に住み込みで働きながら、オートクチュールデザイナーの草分けのひとり・細野久氏のゼミに10年通って勉強しました。33歳の時に独立しましたが、機会あるごとに夜学にも通うなど、今も学ぶ機会を大切にしています。実は明日からパリへ行くのも、18年目の研修のためなんです。
―プロなのに、なぜそんなにまで研修を?
それはもう、お客様のニーズに応えられるものを創りたい一心です。自分が錆び付かないためにも、それから美しいものを見るためにも、研修の場は必要。神戸ファッション協会はもう20年近く、コンテストの入賞者をパリ、ロンドン、ミラノに留学生として送り続けていて、その審査員だったサンディカル校のオルガ・ソーラ校長と、藤本ハルミ先生が「プロも講習を受けられるように」と道を開いてくださったのです。私も本場パリでオートクチュールの先生に教えていただき、自分の技術を再確認したり、こんな方法もあったのかと初心に返ったり、毎回刺激を受けています。
―ご自身の、洋服作りのポリシーは?
「人が主、お洋服が従」が鉄則。着ている人の顔が見えないで、お洋服が歩いているようでは本末転倒。私はお客様の、ライフステージのお手伝いをさせてもらっているんだと考えています。その方の人生の舞台のソデで、その時々にふさわしいお衣装を用意するのが私の仕事。個人個人の発注に応じて作って、年月が経ったらお直しして、というペースだから作った服の数は多くありませんが、お客様に恵まれ育てていただいて今日に至っています。
―思い出深いお仕事など、ありますか?
ある年の暮、「第九」のソリスト(ソプラノ歌手)の付人兼ドレスデザイナーとして舞台のソデに入っていた時、スタッフの方が「来年結婚する時、去年亡くなった母のウェディングドレスを着たいが体型がかなり違う、何とかならないか」とおっしゃって。年明けにドレスを抱えて来られたその方の希望を聞き、ドレスをほどき、デザインして生地を加え、何とか最終の新幹線までに仮縫いを終えました。その方は毎年、「芦屋のママへ」と嬉しいお便りをくださいます。
―映画のワンシーンのようですね。今、注目していることなどは?
映画や写真集が話題のアドバンスト・スタイル! さすがN・Y・マダム。私はあそこまで派手なことはできませんが、ああいうオシャレを肯定できる社会はすばらしい! 日本のアイドルは10代ばかり、若さだけが持てはやされていますが、60歳を過ぎた女性の体には、若い頃とはまた違った美しさがある。還暦を過ぎた女性が、体の線を隠すことなくイブニングドレスを着て、それをタキシード姿の男性がエスコートする…エレガントな大人の世界。年配の女性が着飾るのを揶揄しているようでは、日本の男性は残念ながらまだまだですね。
―確かに、成熟した大人に近づくと思うと、年を重ねるのも嫌ではなくなります。
年を取ることを恐れず、もっと前向きに考えていいと思いますよ。もう流行を追うこともなく自分の好きなファッションで、お友達と美味しいお酒を飲んで、時間にも縛られないで楽しく過ごすって、年を取ったからこそできることです。高齢化社会をマイナスイメージで捉えないで、もっと堂々とオシャレに生きよう!という文化を、神戸から発信できたら素敵ですね。
(2015年6月9日取材)
N・Y・マダムに負けないくらいオシャレでカッコいい石原さんですが、お仕事に関してはどこまでも黒子に徹する、職人気質の人でした。
とみさわ かよの
神戸のまちとそこに生きる人々を剪画(切り絵)で描き続けている。平成25年度神戸市文化奨励賞、平成25年度半どんの会及川記念芸術文化奨励賞受賞。神戸市出身・在住。日本剪画協会会員・認定講師、神戸芸術文化会議会員、神戸新聞文化センター講師。