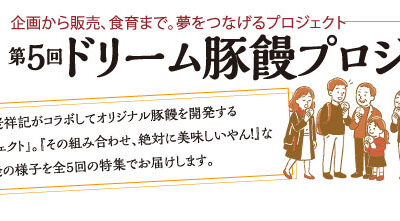1月号

触媒のうた 47

―宮崎修二朗翁の話をもとに―
出石アカル
題字 ・ 六車明峰
宮崎翁が若き記者時代の昭和29年に新聞紙上で有本芳水を取り上げたところ、大きな反響があり、芳水から感謝の便りがあったことを前号に書いた。「岡山へ疎開してからは淋しく暮らしていましたが、あなたのおかげで…」という手紙。
わたし翁にお願いしました。「その手紙を見せて頂けませんか?」と。ところが、
「どこかにあるんでしょうが、すぐには出て来ないですねえ。でも、姫路文学館がオープンした時に何通かを寄贈しました」
ということで、姫路文学館に問い合わせてみた。すると、「二通寄贈して頂いてます」と。コピーを送ってもらおうとしたが、直筆の原稿などはコピーができないとのこと。しかし「お越し頂ければ写真は撮って頂けます」ということで、出かけることにした。
せっかく姫路まで行くのだから、ついでに二カ所の文学碑も訪ねたいと思った。下調べをすると車で行くより現地で自転車を借りた方が良さそうなので電車で。
駅周辺にレンタサイクルがあると思ったのだがなかなか見つからない。何人かの人に尋ねて、やっと「姫チャリ」というのを見つけた。参考のために書いておきますが、これは姫路市の交通計画室が主催しているもので、一日百円で借りることができる。期間限定の試みということだが、結果を見て本格的に実施するとのこと。これは便利です。ぜひ続けて頂きたい。
先ずお城の西北にある姫路文学館へ自転車を走らせる。以前に電話での問い合わせをしたことはあるが、行くのは初めてだった。想像以上に立派な施設である。安藤忠雄氏の設計による建物は無論のこと、展示内容も素晴らしいものだった。もちろん有本芳水のコーナーもあり、芳水が主筆として活躍した色鮮やかな表紙の『日本少年』も多数展示されている。
さて手紙のことである。予め電話でお願いしておいたので、資料は用意して下さっていた。対応して下さった学芸員の甲斐史子さんは親切だった。「久しぶりに宮崎様のお名前に触れて懐かしいです。お元気でしょうか。よろしくお伝え下さい」と。
手紙は二通。筆圧を感じさせない軽いタッチのペン書き。60年ほども昔のものだ。用紙は時を経てむかし色に変色しており文字も薄くなっている。いずれもが心情あふれるものだが、特に昭和30年に書かれた、原稿用紙五枚の手紙は胸を打つ。
ゆっくりと読ませて頂き、撮影する。
帰宅してパソコンに取り込み、拡大して書き写す。その要所。
《五日学校から帰りますと(私はこちらの短大に教鞭をとっています)貴著が届いておりました。》
ここでいう“貴著”とは宮崎翁の処女出版『文学の旅・兵庫県』(昭和30年刊)のことである。
《四五日前関学の藤木氏が来訪されて神戸新聞に連載された文学アルバムが上梓されることになったと聞きました。是非拝読したいと思っている折からでした。早速封を切って一讀し、さらに一字一字すいつけられる心持で精讀し、また写眞も見ました。》
“写真”とは、宮崎記者が撮った、芳水生家の写真であろう。家の前に三人の子どもが遊ぶ姿を配した趣のある写真だ。
《夢でなくては見られぬこと、すぎ去った過去のこと、それが、はっきりと活字になり、写真で浮き出され、美しい本になっているのですから、本当にうれしく思いました、夢よもう一度…それが貴著によって実現されたのでした。》
この手紙の時、芳水は69歳だ。そして宮崎記者は33歳。丁度親子ほどの年齢差。しかしこの手紙文を読むと、一時代を築いた老詩人が若き新聞記者に送るような文面ではない。あまりにも丁重に感謝の気持ちを述べている。しかも本心からというのがよく分かる。わたしは、エンピツで書き写しながら胸の中に熱いものがこみ上げてくるのを抑えられなかった。
《文献によってさへ骨の折れる仕事です、それを町から村へと縣内至るところ資料を求めて歩き廻り、これだけのことをされた貴兄の努力には、頭が下がります。》
いつも翁がおっしゃっている「現地に行く」ことの大切さ。わたしはなかなか実践できないでいるが。
《私ごときもの、世に忘れられたもの、野末の名なし草にすぎない私までも取り上げて戴き光栄の至りです。耽讀数刻、老妻から夕餉を知らされても、知らぬ顔で讀んだことでした。讀み終わって瞑目すると、闇の中に、書中に出て来る人人―親しくした 人々の顔が浮んでくるのでした。》
なんと心のこもった感謝の手紙だろうか。翁がおっしゃっていたことは当然ながら偽りではなかった。
このあと昔交わった文人の思い出話が三木露風を始めとして縷々続き、
《こんなことを書き出すと限りがありません、この辺でやめましょう。老妻に貴著を見せると、花袋、夢二、牧水、白秋、夕暮、露風を知る老妻は、皆な故人になられて…と涙ぐんでいました。》
と続く。そして次のように手紙は閉じられる。
《私は来る十一月十一日姉の孫が結婚するので大阪に参ります 帰途十三日(日)神戸に寄り、元町をブラついて、正午頃姪(元町北側松井と言う洋品店、二男が本春関学を出て神戸新聞社にお世話になっているそうです)のところへ顔を出してから帰ろうと思っています。
有本生
宮崎様 》
芳水さん、「…帰ろうと思っています」と書きながら実は、ついでに宮崎記者に会いたいという気持をチラリと出しておられる。単に文人と新聞記者というだけの関係ではないものが生じていたのだろう。
文学館を見学したあと、“姫チャリ”でお城の北にあるシロトピア記念公園を目指した。そこに文学碑があるのだ。
わたし、姫路城には何度も行っているが、城の北や東を訪れるのは初めてだった。思いがけず静かなところだ。観光客がいない。散策やジョギングする地元の人のみ。横から眺める姫路城もなんだか油断をしているようで、のどかだ。
文学碑はすぐに分かった。大きく立派な碑だった。周りを一巡りして早速写真を撮る。しかし困った。秋の日差しによる木立の葉影が邪魔をしていい写真が撮れない。季節と時間帯と天候によっては撮影に適さないことがあるんですね。素人の悲しさでした。刻まれている詩は「白鷺城回想の賦」と題された三木露風との共作によるもの。こんなのは珍しいと思うがそのことの詳細は略す。興味のある方はお調べ下さい。刻まれている文字は芳水でも露風でもなく、『わが心の有本芳水』の著者でもある後藤茂氏によるもの。
次に目指したのは、芳水生誕の地、飾磨区玉地。
途中、姫路市役所近くの定食屋に入って昼食。昼時を外れていたので客は少なく、玉地天神社への道を尋ねた。教えて頂いた通りに約20分ほど走ると、家並みを隔てた道の向こうに社叢らしきものが目に入り、出会った人に尋ねてみた。すると「あそこです」と。
そこに芳水の詩碑があるはずだった。境内へ入り一望する。しかしそれらしき碑は見当たらない。本殿にお参りをしてから、もう一度境内をくまなく探して歩いた。けど見つからないのだ。『わが心の有本芳水』によれば、灯台型の大きな詩碑が建っているはずなのだが。尋ねようにも社務所はない。うろうろしているところへ年配のご婦人がお参りに。「いつもお参りされるのですか?」と声をかけてみた。すると「ハイ毎日」と。ご近所の人だった。で、詩碑のことを尋ねると、指を差されたのが境内の外だった。道を挟んであちら側に建っているのが見える。移転していたということだろうか。このご婦人、「芳水さんなら、生家跡にも碑がありますよ」と道順をお教え下さった。それは知らなかったのでありがたかった。
灯台型の詩碑は、きれいに整備された地にあった。背景には入り江からの水路が情緒を醸し、漁村の名残を残している。いい風情だ。
刻まれた詩文。
播磨はわれの父の国
播磨はわれの母の国
播磨の海にともる灯の
その色見れば泪ながるる
有本芳水
これは芳水自筆の字で刻まれている。一字一字丁寧に書かれていながらリズム感のある流れるような書体だ。
これも日差しの加減でいい写真が撮れず残念。
次に、先ほどのご婦人が教えて下さった芳水生誕地へ。
すぐに分かると思っていたのだが、いくら探しても見つからない。自転車でその辺りを何度も何度も巡った。道は昔の風情を残していて狭く、もしも車で行っていたならどうにもならないところだった。宮崎翁が若き日に訪れた町の名残があちらこちらに残っている。そんな中をグルグル回るが、それもまた良し。何人目かに尋ねた人が「ここから三軒目」と。なんだ、何度も前を通っていたのに。わたしの一人合点で、碑は古いものと思い込んでいたのだ。そのイメージで探していたのだ。実は新しかった。それが新しい家の前にスコンと無表情に立っていたのだ。
飾磨の海近く
有本芳水ここに生る
側面には「平成五年十月吉日 玉地自治会」とある。
ここがあの、宮崎記者が昭和29年に撮影した芳水生家の跡にちがいない。しかし、その古い家はなく、瀟洒な現代建築の家になっていた。芳水に所縁の人がお住みなのだろうが、わたしはお訪ねするのを遠慮してその地を離れた。
終わりに宮崎翁が芳水さんから聞かれたエピソードをもう一つ。
「吉屋信子は競馬好きで有名ですが、実は初め、有本さんが戯れに連れて行って、それが病みつきになったそうですよ。それから、菊池寛もね」
そういえば『笛鳴りやまず』の菊池寛の項は、競馬に関することに多くページが割かれている。しかし自分が最初に誘ったとは一言も書かれていない。


宮崎翁に宛てた芳水の書潤(封筒は別便のもの)

飾磨区にある芳水の詩碑

昔の風情を残す生誕地の町並み

姫路城にある文学碑「白鷺城回想の賦」
■出石アカル(いずし・あかる)
一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。