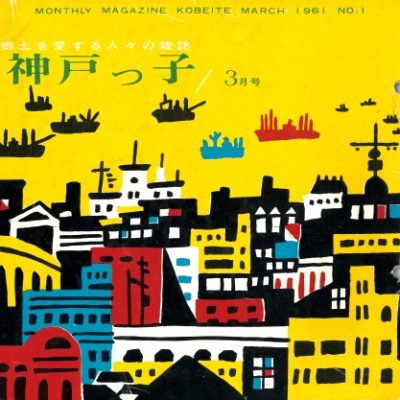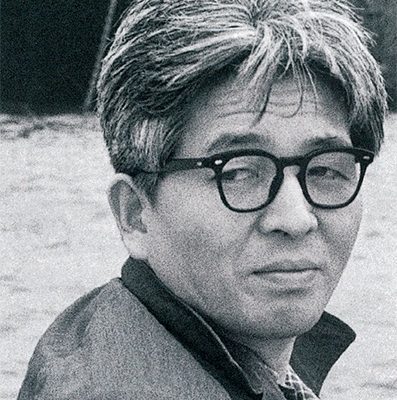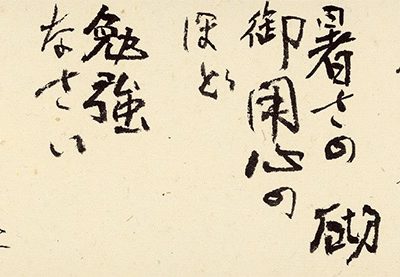1月号

700号 記念寄稿|神戸の光と影 〜わたしの神戸の物語から〜 作家 玉岡 かおる
神戸の光と影 〜わたしの神戸の物語から〜
作家 玉岡 かおる
神戸文学賞受賞作『夢食い魚のブルー・グッドバイ』で文壇にデビューしたのが平成元年。以来、年に一冊のペースで作品を世に送り出してきた。まさに平成は、私の作家としての人生時間だったと思っている。
その平成最終期にあたる一昨年、『花になるらん ~明治おんな繁盛記』(新潮社)で、開港まもない神戸の街の姿を描いた。神戸が港の界隈だけをさす、本当に小さなエリアでしかなかった時代の物語だ。
貿易商であり美術商でもある高島屋の、女主人をモデルとしたヒロイン雅は、禁門の変や東京遷都で灯の消えたような京をなんとかしようと、神戸へビジネスチャンスを探しにやってくる。貿易相手の英国ではお茶が大流行。神戸港からも宇治茶が大量に輸出されていることを知るが、彼女はそのお茶を楽しむ器に目を付ける。京には、どこの国も真似のできない洗練された工芸技術を誇る職人たちが残っており、これを促進することは千年を超えて築かれてきた日本の伝統や文化そのものを守ることになるのである。
当時、日本の陶器は海外では「サツマ」という単語になっていた。パリ万博で薩摩藩が御用窯の焼き物を展示した成果である。京で焼かれたものを「京薩摩」。京都から運搬中に壊れることが多いことから神戸の港近くで焼いたものを「神戸薩摩」といい、これらは欧米で一世を風靡した。
取材では数々の名品に出会ったが、彼女の店が実際に商った品で、川崎造船所初代社長・松方幸次郎が欧州の政府要人に贈ったみごとな刺繍のタペストリーを見た時は震えがきた。そう、拙著『天涯の船』(新潮社)では、まさにこの幸次郎が、潜水艦の設計図を求めて美術品を手がけ、名高い松方コレクションを形成する物語を小説にした私なのだ。
さらに、貿易といえば私の代表作『お家さん』(新潮社)で書いた神戸の総合商社鈴木商店の活躍も忘れることはできない。
これら、ちっぽけな地面しか持たない神戸が海外を相手に日の出の勢いで発展していった物語は、まさに光の時代といえるだろう。歴史に埋もれた記憶に光を当て、読者の皆様の心に、神戸への誇りを蘇らせることができたことは作家として幸せに思う。
だが、光さす場所には必ず影ができる。
神戸の影。それは、この狭い土地に一気に流入した人間の、実際の暮らしである。
開港当時は数千人にすぎなかった神戸人が百万人規模にふくれあがり、一時は東京の人口にせまる日本第二位になったのだから、生活レベルはとても文化的とは言えなかった。たった四畳半の貸間に親類家族七人が暮らすなんてざらだったし、労働者の福利厚生もなく、怪我でもすればたちまち困窮。スラムに身を寄せ、その日その日をしのぐしかない。いちばんの犠牲になるのはどこの世界でも子供たちだ。神戸の貧民窟は日本最大になった。
うそぉー、おしゃれな都市神戸にそんなことが? と驚かれようが、事実である。
そしてそんな”影”に沈んだ人々に、愛の手をさしのべた男がいた。賀川豊彦。生協や共済の生みの親であり、ノーベル賞にノミネートされた偉人である。
けれども、人々が痛みを癒やし、神戸が豊かになるとともに、彼も忘れられていった。つまり彼は、神戸の影を拭い去り、幸せにして去った男、と言い換えられるだろう。
今、私は、その賀川の妻ハルを通して、歴史の再評価に挑んでいる。
『春いちばん ~賀川ハルのはるかな旅路』(月刊誌『家の光』に連載中)がそれだ。
令和の幕開けとともに開始した連載だが、完結するにはまだあと二年はかかる。待てない、という方には定期購読を勧めるしかないのだが、神戸人ならこの人をけっして影に沈めたままではいけない、そんな思いに突き動かされてペンを進めている。光と影、二つで完結する真の神戸。ぜひ応援を願いたい。
「花になるらん〜明治おんな繁盛記」は文庫になって新潮社より令和2年3月刊行予定。