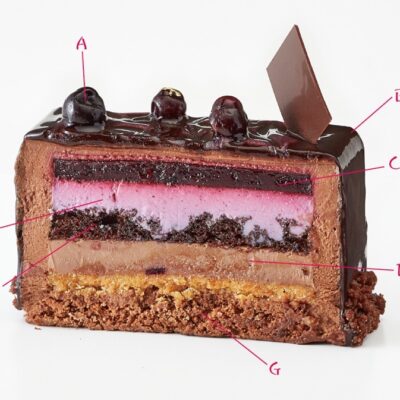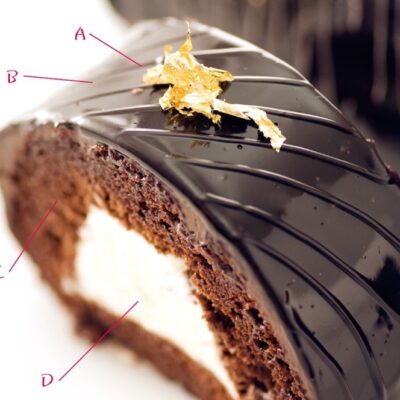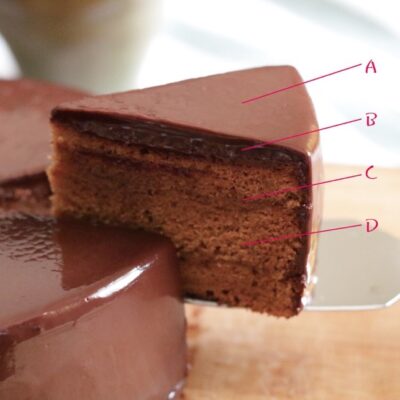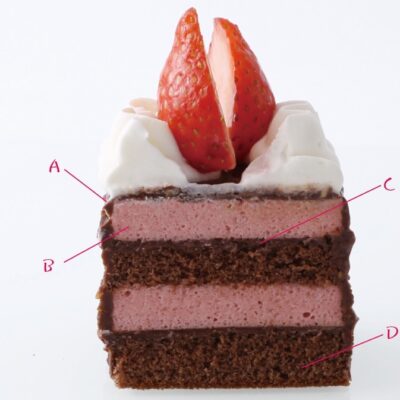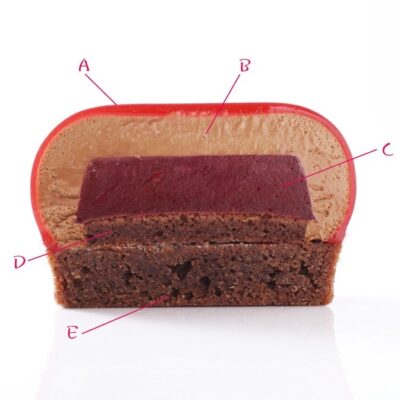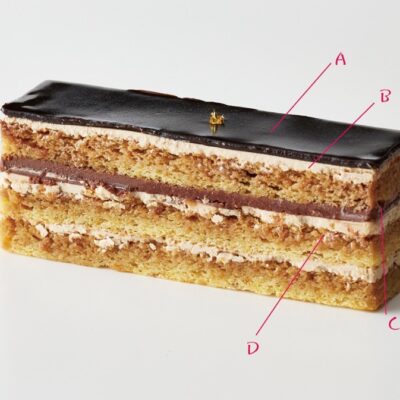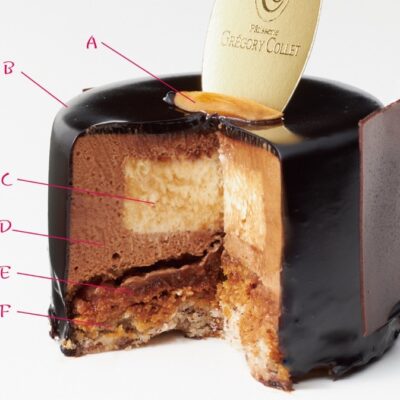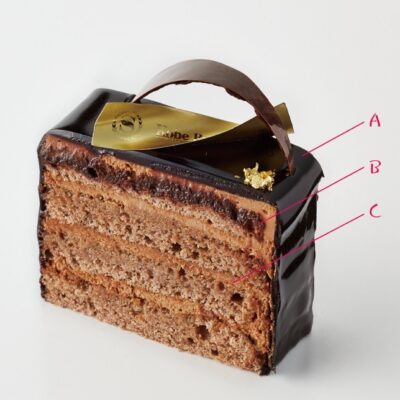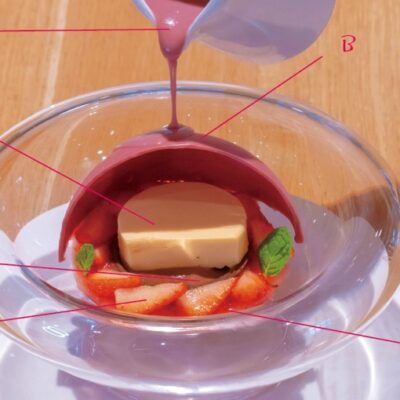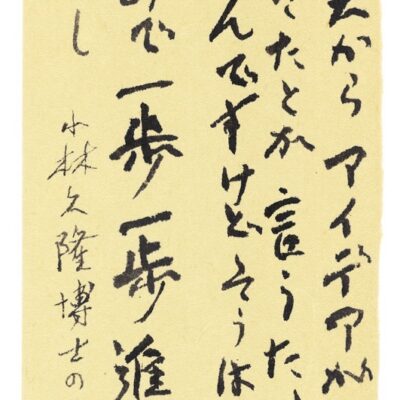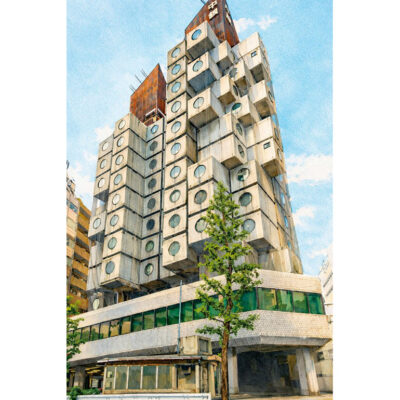2月号

映画をかんがえる | vol.23 | 井筒 和幸
84年の初夏に封切られた『晴れ、ときどき殺人』は角川三人娘の一人、渡辺典子主演のただのお伽話に過ぎないが、せめて異色な風合いのニューシネマにできないものかと、音楽家の松任谷正隆さんにも出演してもらった。それも何と!女性ばかり狙う殺人鬼の役で、このミステリーの最後を飾ってくれたのだ。彼がNHKドラマで、初めて俳優として自然体で役を愉しんでるのを見ていたのでお願いしたのだ。俳優は如何に自然に自身の人格の一部を曝け出せるかだ。彼の演技には鬼気迫る瞬間があり、彼なりの心の暗部を垣間見た気がした。演技はプロもアマチュアも関係ないなと思えた現場だった。
この年の後半は、人気絶頂の漫才コンビ、西川のりお上方よしおの御両人らと流行りのギャグパフォーマンスビデオの制作もしながら、相変わらず映画三昧の日々だった。映画を見ないと生きている気がしないし、映画館はボクの精神安定剤だった。
8月には『零戦燃ゆ』というノンフィクションの戦争モノも見た。『仁義なき戦い』(73年)の名脚本家、笠原和夫の作品だったからだ。でも、製作者の大平洋戦争の反省メッセージが伝わってこなくて、がっかりだった。「笠原さん、この戦争兵器をどう考えろというんですか」と悩んだ。ボクもいつか戦争モノを撮るか知れないが、人間は忌まわしき戦争をなぜ映画で見たくなるのか?そこがまだ解っていなかったのだけど。
気楽な映画もたくさん観た。すべての映画が監督の勉強だった。ロバート・レッドフォード主演の『ナチュラル』(84年)は戦前のアメリカの野球界が舞台で、ある事件の為に身を引いていた選手が遂にメジャー戦に復活し、心のしこりを消散させてホームランをかっ飛ばす。映画のカタルシスを久しぶりに学んだ瞬間だった。
『ライトスタッフ』(84年)も封切りを待ち望んだ一作だった。有人宇宙飛行を目指して訓練する7人のパイロットの実話だ。宇宙飛行士の「正しい資質」に従って訓練し、音速越えに挑む者たちをしっかりと捉えていた。オレには監督の才能以前にその資質はあるのか?と自分にも問い質しながら画面を追っていたような気がする。
クリント・イーストウッドが製作主演した『タイトロープ』(84年)も実によく出来た、『ダーティハリー』(72年)の彼より屈折した女好きな刑事の心の裏に迫るサスペンス劇だった。彼を嘲笑うように猟奇殺人鬼が彼と遊んだ女たちを次々に狙っていく。女優たちが身体を張って役をこなしていた。エロス、猟奇、戦慄、冗談、この短編にも意外に娯楽の要素がほど良く詰まっていた。
テレビドラマでは、長年続いた石原軍団出演の「西部警察」シリーズも終わりを迎えていた。でも、ボクはこの警察モノには全く気がいかず、一、二回いい加減に見ただけだった。あの拳銃アクション場面はよその国のようで、日本のリアリズムがなかったからだ。秋になっても、ボクは毎週のように映画館に足を運んで画面作りの勉強をした。特に、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(84年)はイタリアのマカロニウエスタンの巨匠作品で、デ・ニーロ主演の禁酒法時代のニューヨークギャングの話なのでかなり期待していた。でも、その冗漫な展開とどうにも画面に馴染まない大袈裟な音楽に堪えられなくなり、2時間余り見たところで一度、劇場のロビーに出て休憩した。そして、次の回で最初から見直したのだが、やっぱりつまらなかった。後年、テレビ放映でまた見たが、気が散るばかり。これはボクには反面教師になった。
年末になると、軽佻浮薄な時代を皮肉るような、『ゴーストバスターズ』(84年)がアメリカから半年遅れでやって来た。騒々しいだけの年末にふさわしく、社会の理不尽を鼻で笑ってるようでそれが愉快だった。ラストで、バスターたちが魔界の破壊神に「どんな方法で滅ぼされたいか想像してみろ」と迫られ、マシュマロマンが現れたのには感心した。アメリカではここで手を叩いて笑うと聞いていたが、渋谷の映画館はそうでもなかった。日本人が笑いまくるものを見たかった、いや、撮りたかった。


PROFILE
井筒 和幸
1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm映画『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD発売中。