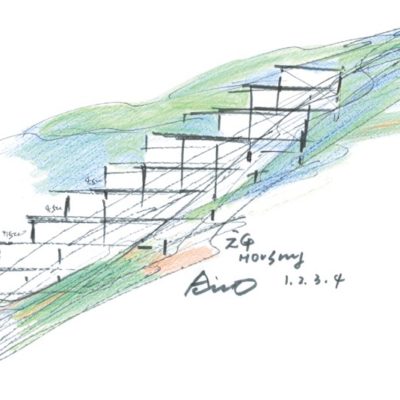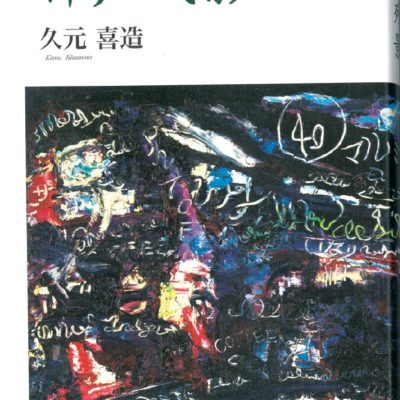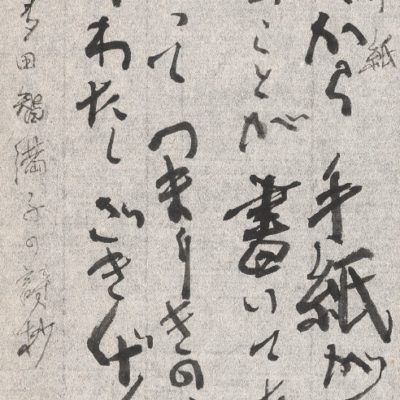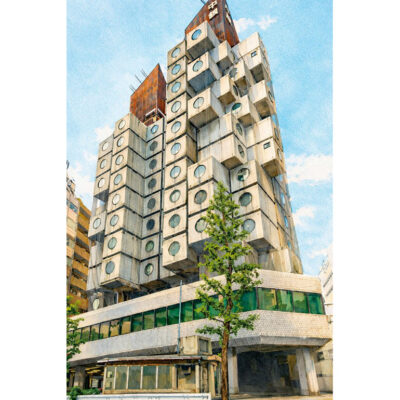12月号

映画館で叶えられるゴッホとの対話 ~映画「永遠の門」で知る〝ゴッホの真実〟

生きているときには、その創作活動や作品が、世間にまったく受け入れられず、亡くなった後に、作品の評価が高まり、世界中で、その名を知らない人がいないほど有名になったという芸術家は少なくない。37歳の若さで亡くなったオランダの画家、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890年)は、その代表的な一人といえるだろう。
現在、公開中の映画「永遠の門 ゴッホの見た未来」は、無名だった孤高の画家が、どのように絵画と向かい合いながら生き、そして死んでいったかを、彼の視点から、美しい映像で克明に辿っていく。
米国の名優、ウィレム・デフォーがゴッホ役を熱演。〝狂気の世界〟の中で創作に没頭するゴッホが乗り移ったかのような鬼気迫る演技は圧巻で、昨年のベネチア国際映画祭で最優秀男優賞に輝いた。監督は、画家でもあり、「潜水服は蝶の夢を見る」(07年)で、カンヌ国際映画祭監督賞を受賞した名匠、ジュリアン・シュナーベル。画家としての誇りを懸け、シュナーベル監督は映画に登場するゴッホの作品を自ら描き、また、デフォーとともにゴッホの筆使いまで研究し学んだといい、その成果を、劇中でデフォーが臨場感豊かに演じ披露している。
晩年のゴッホが、憑りつかれたようにキャンバスに向かい、力強い線を一心不乱に描き上げていく姿は印象的だ。
「なぜあなたは花を描くの?本物の花の方が美しいのに」。
花を写生しているゴッホをそばで見ていた女性が質問すると、彼は静かに、こう答える。
「この花はやがて枯れるが、僕の描いた絵は残るから」と。
1987年、ゴッホの代表作「ひまわり」を、日本の生命保険会社が約53億円で落札したニュースが、当時、世間を賑わした。
ゴッホが実際に写生したひまわりの花は、枯れて、もうこの世に存在しないが、彼が描いた「ひまわり」は、約130年が過ぎた今でも世界中の人が見ることができる。
「僕の描いた絵は残る」と語った彼の言葉は嘘ではなかったのだ。
一世紀以上の時を超え、ゴッホの絵画が神戸で蘇る。来年1月25日から、ゴッホの代表作など約40点を並べた「ゴッホ展」が神戸市中央区の兵庫県立美術館で開催される(3月29日まで)。彼の〝筆使いや息遣い〟までを確かめることができる貴重な機会になるだろう。
この映画は実はゴッホ展から生まれた。シュナ―ベル監督は、パリのオルセー美術館で開かれていたゴッホ展に、友人の脚本家、ジャン=クロード・カリエールを誘った。ゴッホの自画像を間近で見たカリエールは「まるでゴッホと監督、私の3人で向き合っているようだった。作品の声が聞こえてきた」と言う。その瞬間、この映画の製作が始まった。
「なぜ、絵を描くのか?未来の人々と自分が見たものを分かち合いたいから」
劇中、ゴッホが語る、このセリフの真意を噛みしめながら、神戸の展覧会場で、彼の作品とじっくりと対話してみたい。

© Walk Home Productions LLC 2018

© Walk Home Productions LLC 2018

オスカー・アイザック演じる画家、ゴーギャン(左)とゴッホとの関係も対比的に描かれる
© Walk Home Productions LLC 2018

”北欧の至宝”と呼ばれるデンマーク出身の俳優、マッツ・ミケルセンも聖職者役で登場する
© Walk Home Productions LLC 2018

© Walk Home Productions LLC 2018
【筆者プロフィール】
戸津井康之(とつい・やすゆき)
1965年10月4日、大阪府堺市生まれ。元産経新聞文化部編集委員。大学卒業後、日本IBMを経て、1991年、産経新聞入社。大阪本社社会部記者、大阪、東京本社文化部記者、文化部編集委員を経て2018年に退職し、現在、フリーランスの記者。産経新聞記者時代は紙面とネット連動の連載コラム「戸津井康之の銀幕裏の声」「戸津井康之のメディア今昔」などヒットコンテンツを手掛ける。