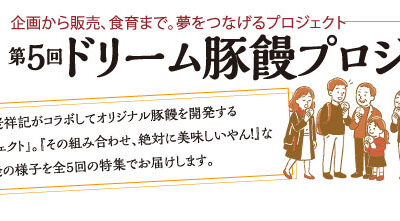11月号

触媒のうた 45

―宮崎修二朗翁の話をもとに―
出石アカル
題字・六車明峰
92歳、宮崎翁のお話。
「誰知らぬ人がないくらいに有名だった有本芳水(ほうすい)ですがね、何十年の間ぷっつりと消息が途絶えていました。けど、疎開先の岡山にご健在だと知って…」
有本芳水(1886年~1976年)。詩人、歌人。姫路市出身。早稲田大学卒業後「実業之日本社」に入り、『日本少年』の主筆として活躍。同誌に毎号発表した少年詩がブームになる。
「昭和28年でしたが、芳水さんのことを神戸新聞に書きました。すると大きな反響がありました。『えっ!芳水はご健在だったの?』と。
『芳水詩集』(大正3年・実業之日本社刊)というのがある。これが『日本少年』に連載した少年詩集。三百五十版も重ねる大ベストセラーだ。少年時代、この詩集に影響を受け、後に有名文学者になった人は甚だ多い。
「昔古本屋で買ったものですがあなたに差し上げます」と言って翁が持ち出して来られたのが、その詩集。
「うわーっ!、これは迂闊に触れません」
酸化がひどくてホロホロと崩れてしまいそうだ。表紙も奥付もない。ページを開くと解体してしまいそうなのだ。で、わたし、それは大事にとっておいて再々復刻されたものを入手して読みました。この何回も復刻版が出たというのも、ひいては宮崎翁の触媒仕事のなせるところなのでしょうか。
装丁がいい。竹久夢二だ。そして「序」の言葉。
《少年、少女の愛らしき口より、われに詩集を編め との請(せ)めいなみがたく、茲(ここ)にわが幼き詩集『芳水 詩集』はなりぬ。
(略)
旅にしあればしみじみと
赤き灯かげに泣かれぬる。
されば人生は旅なり、さらばいつまでもかく歌ひつ づけむ。
月夜船唄をききつつ
筑前博多の客舎にて
二月十七日 著者 》
漢字にはすべてルビが振られている。感傷的な文語文で、納められている詩も文語体で書かれており、竹久夢二の表紙絵と相俟って、大いに抒情的、感傷的だ。わたしは、「ほう、これが当時の少年たちの胸を揺さぶった詩なのか!」と納得。いかにも大正の感傷的ロマンだ。宮崎翁、「お読みになればあなたはお笑いになり、詩としてお認めにはならないでしょうが…」とおっしゃるが、たしかに今日の少年たちに受けることはないだろう。
芳水については、前号の野坂昭如同様、『環状彷徨』に詳しく紹介されていて、それは随分洗練された記述になっている。しかしわたしは、翁の処女出版だった『文学の旅・兵庫県』(昭和三十年)の文章の方が温もりがあって好きだ。
『文学の旅・兵庫県』については、この連載の第一回と二回に「本の背中」と題して詳しく書いた。面白い話です。ぜひ本誌のバックナンバーをお読みください。
で、「芳水生家」と題された同書の個所。
《赤き夕日のてるところ
昔なつかしふる里に
われも旅よりかへり来て
小川のほとりとめ来れば
野は秋草にみだれたり
そうした少年詩の一節がわたしの口からこぼれる。大正も末期の生れであってみれば、私にとってこの詩の作者が、幼いころへの郷愁をいざなう人だとはとてもいえないのであるが、その詩作品はどこかなつかしい望郷のしらべを、切々と訴えて来るのである。
詩人としてよりも、明治三十八年に尾上柴舟や前田夕暮、若山牧水らと車前草歌会を作り、当時の歌壇に活躍したという名で記憶していた私にとって有本芳水氏が岡山県上道郡浮田村に健在であるということを知ったときは大きな喜びであった。 さっそく私は氏にあてて生家について問合せの手紙を書き、姫路市飾磨区玉地にその家がのこっているということを知ることができた。》
いいですねえ、この文章。若き新聞記者の活き活きとした心持があふれています。添えられた宮崎記者撮影の芳水生家の写真もいい。翁はカメラの腕前もなかなかのものなのだ。
もう少し続きを、
《山陽電車の飾磨駅に降りた私は、歩を早める。秋のある夕暮れどきである。古い港町の面影がここかしこにのこり香を漂わせている。 (以下略)》
全文載せたいがそうもいかないので興味のある方は図書館ででもお読みください。
翁は芳水のことを「生きた文学史でした。明治・大正文壇の裏面史や昭和の文学揺籃期のことをぼくに色々と話して下さいました。今となってみれば録音しておけばよかった」としみじみ。
つづく


芳水詩集(右は復刻版)
出石アカル(いずし・あかる)
一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。