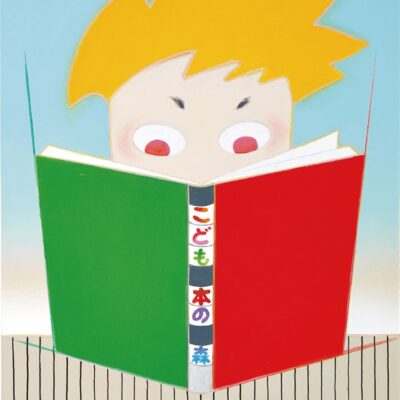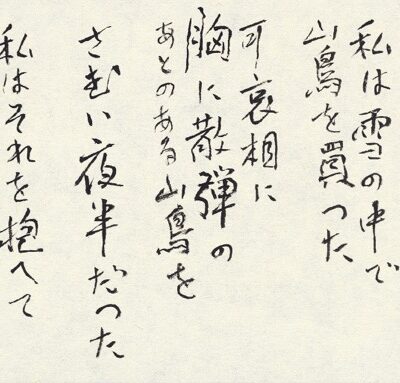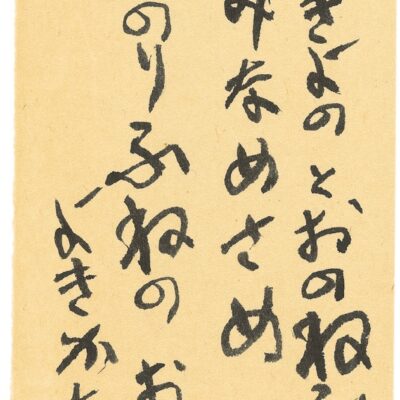3月号

映画をかんがえる | vol.12 | 井筒 和幸
人間らしいオモロい奴、人間に見えないケッタイな奴が次々に現れる、そんなアメリカン・ニューシネマの洗礼を受けて、知らぬ間に二十歳を過ぎ、70年代の日々の喜怒哀楽を映画と共に生きられたのは、映画と無縁な人よりは幸福だったかも知れない。大阪や京都や兵庫や和歌山だろうと、そこの映画館で半月おきに替わる作品に出会うためなら、何処でも足を伸ばし、ご飯を食べる時間も金も惜しんで、その光と影の世界に没入したものだ。ボクの眼前では、日々の誰かの現実と、銀幕の中の誰かの現実が入れ替わり立ち代わりしていて、現実の憂さや切なさを慰められ、怒りを鎮められ、苦しみが和らぐ、かと思えば、銀幕の中の悦びや怒りに共感し、自分の感情も振り回された。でも、どっちの現実も、心を鍛える途中の自分には大事なことだった。改めて思うが、そんな幻影に遭遇してなかったら、今、どうしてたか見当もつかない。
18世紀のまだ英国の植民地だったアイルランド地方出身の、バリーという青年の流転の半生につき合わされて、こっちまで何十年も歳をとったような気になった傑作がある。スタンリー・キューブリック監督の『バリー・リンドン』(76年)だ。前作の『時計じかけのオレンジ』(72年)は、暴力と性欲の限りをつくす不良青年が専制国家から精神治療の実験台にされる近未来を描く、あんまりいい気分がしない映画だった。でも、このバリー青年の方は、恋敵の貴族と決闘して勝ち残り、母と暮らす農家を出て、大英帝国軍に入隊して何度もの戦争に参加し、詐欺師にもなり、遂にはリンドン伯爵婦人の後婿になって爵位ももらって息子も生まれるが、また決闘して片足を失って財産も失って、不運に翻弄される成り上がり者の話で、貴族の醜さやだらしなさをリアリズムで暴いた。電灯がない時代を描くためにロウソクの光で撮ったと噂になった。3時間見続けるとボクの心も空っぽになっていた。一緒に観た友人が「人間、立って半畳、寝て一畳、天下取っても二合半やな」とうそぶいた。
「無常」や「空」の仏教観に惹かれたのはこの頃からだ。アメリカは介入したベトナム戦争に敗北したし、沖縄から爆撃機を飛ばせて戦争に加担していたはずの日本もオイルショックで経済成長は止まったものの、途端に平和を求め始め、無常感どころか、大人も若者も一億総中流を目指して自分の幸福探しに精一杯だった。でも、ボクの空っぽの心は世の中の虚栄にはついていけず、自分の映画作りもうまく運ばず苦闘していた。そして、田舎の喫茶店で煙草をくゆらせる度、世間にはぐれていても、血が騒ぎ身体も震えるような社会を射る映画を見たかった。そこに現れたのがマーティン・スコセッシ監督の『タクシードライバー』(76年)だ。主人公はベトナムの地獄から五体満足で帰還したが戦争後遺症で不眠症を患い、何をして生きたらいいのか悩んでいる海兵隊上がりの、ちょっと、いや、かなり外れた青年だ。ベトナム体験はないが、知らぬ間にはみ出てしまったボクと気分が似ていて、すぐに画面の中のニューヨークを走る彼のタクシーキャブに同乗できた。彼は流しの運転手をしながら自分に何が出来るか考えた末、次期大統領候補の暗殺を思いつく。しかし、社会はそんなに甘くない。すぐに諦めて、今度は下町に巣食う怪優ハーベイ・カイテル演じるポン引き男や売春業者を始末しに行く。
この“怪物映画”はボクの血肉になっている。バーナード・ハーマンのやるせない主題曲はいつも、生きあぐねるボクの心を泣かせる。何十回観たことだろう。後年、テレビ番組でニューヨークに行き、最後の銃撃シーンのパロディーを16ミリで撮り、3分間の『タクシードライバー・88』を仕上げた。もしもロケ中、デ・ニーロさんに見つかっても歓迎してもらえるように、主役の若者の頭はモヒカン刈りにしてもらった。結局、本人には出会えなかったが。
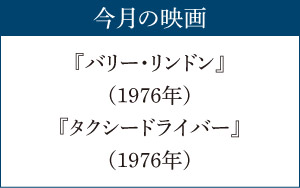

PROFILE
井筒 和幸
1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD、2021年11月25日発売。