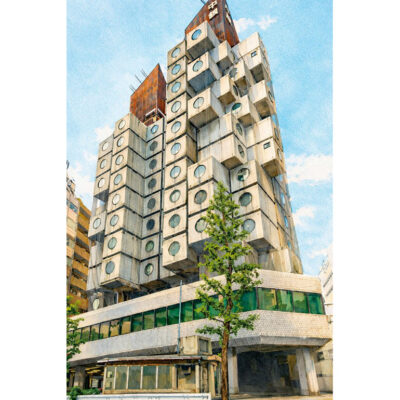7月号
神戸鉄人伝(こうべくろがねびとでん) 第55回

剪画・文
とみさわかよの
詩人
鈴木 漠(すずき ばく)さん
余白が目に心地いい紙面。明朝体の活字を追うと、まず言葉が音になって響く。咀嚼するより、口ずさむ方が情景が見える。ちょうど唱歌のように…。現在主流の散文詩に対して、韻を踏んだ詩を作り続ける鈴木漠さん。日本詩の押韻を新しい形式で試みた詩集で、第十四回日本詩人クラブ賞に輝いた実績をお持ちです。また連句にも長く取り組んでおられる鈴木さんに、お話をうかがいました。
―「詩」と出会ったのはいつでしょう?
一番最初は小学校6年生の時、教科書に出ていたロングフェローの訳詩です。いいな、と思って詩が好きになりました。普通は中原中也あたりから詩の世界に入る人が多いですが、私は上田敏や堀口大学の訳詩が入口でした。中学生の頃は北原白秋が好きで、文庫本が真っ黒になる程に繰り返し読んでいました。投稿を始めたのもこの頃です。
―一昔前の翻訳詩は古めかしい、でも美しい日本語でした。
たとえば中原中也の訳したランボーの詩は、仏文学ではなく日本文学だと思います。上田敏の「秋の日の ヴィオロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し」(ヴェルレーヌ「落葉」)などは、よく知られていますね。このような優れた訳詩は、それ自体が日本文学です。訳した人に古典の知識があったからこそできる、名訳ですよ。
―日本語での詩作が、定型に始まるのは何故ですか。
日本ではずっと、「詩」は漢詩を意味していました。明治時代になって、西洋詩の影響の下、それまでの短歌・俳諧などの定型の表現とは異なる新しい詩形式が模索されます。西洋のpoetryを日本語で作ろうとすると、韻を日本の詩形に取り込まないといけない。そこで七五調、五七調の音数律による新体詩が提唱されます。守るのは音節の数だけなので定型時代よりかなり自由な表現ができるようになり、島崎藤村の時代に日本の近代詩が確立しますが、情緒に流れる傾向も出てきます。その後、口語自由詩が確立され一切の形式が無くなり、この流れが散文調の現代詩に続いている。私はそれに逆らって、新しい形式の押韻を試みています。
―新しい形式の押韻というのは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
簡単に言うなら、西洋の詩の形式、ソネット(脚韻十四行詩)やテルツァ・リーマ(三韻詩)を、日本語で作るんです。行数を守って脚韻を踏む。声に出して読めばすぐわかります。日本語は脚韻より頭韻の方が響きやすいんですが、私は敢えて脚韻で詩作しています。
―詩のほかに、連句にも力を入れておられるとか。連句と言うと、複数の作者がルールに従って次々に句を詠む、松尾芭蕉や与謝蕪村も実践した形式の文芸ですね。
連句は共同制作なので思わぬ世界が展開することがあり、それが楽しい。松尾芭蕉は全国行脚して仲間と連句を詠みましたが、対して井原西鶴はひとりで一千句以上を詠みました。ある意味西鶴は現代文芸を先取りしていたとも言え、明治以降の文芸は個人プレーの小説や詩歌が台頭し、連句は忘れられていきます。これを復興したいという思いで、神戸市内で町道場のような形で教えていますが、なかなか短歌や俳句のようには普及しませんね。
―韻を踏んだり、連句を実践したり、敢えて時流に逆らった活動の目的は何なのでしょう?
散文化した現代詩へのささやかにして最後の抵抗ですが、電子書籍などというものが出てきた現代に活字表現としての文芸に取り組むこと自体が、そもそも時代錯誤なのでしょうね。活字が遠のくその一方で、押韻詩がラップという思わぬ形で復権したりもしています。これからは画面を使ったビジュアル表現が出てくるかもしれない。視覚表現も時代とともに変化していき、また新しい形式の詩が生まれるのかもしれません。
(2014年5月27日取材)
「活字文化の滅びに殉ずる」と言いながらも、鈴木さんの試みと抵抗は、これからも続きます。
とみさわ かよの
神戸のまちとそこに生きる人々を剪画(切り絵)で描き続けている。平成25年度神戸市文化奨励賞受賞。神戸市出身・在住。日本剪画協会会員・認定講師、神戸芸術文化会議会員、神戸新聞文化センター講師。