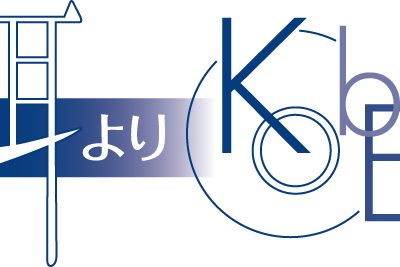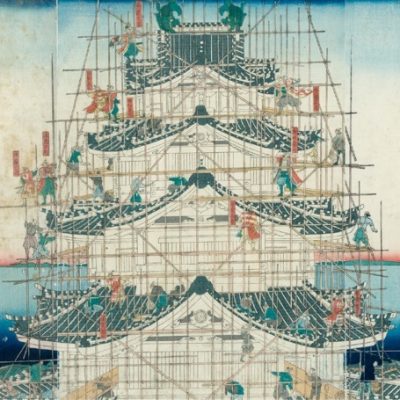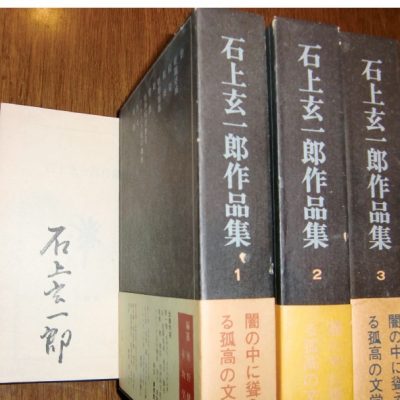9月号

伊藤ハムと神戸
「神戸で創業したことは幸せだったと思う」と伊藤ハム創業者・伊藤傳三氏はかつて語った。瀬戸内海の海の幸、灘五郷の銘酒、明治開港後、居留地に住む西洋人たちが好んだ文明開化を象徴する新しい食品、洋菓子、牛肉、華僑が作る中華料理…、神戸では味に対する鋭い感覚が引き継がれてきた。「そのど真ん中で食肉加工業を営むのだから、最初からひと味もふた味もすぐれたものを提供しなければ商売はやっていけない。私は神戸に来てずいぶん味覚の勉強をした」
灘区で誕生した人気商品〝セロ〟
伊藤氏が灘区大和町の工場で「セロハンウインナー」の開発に成功したのは1934(昭和9)年であった。魚肉ソーセージの失敗を経て、中身づくりと包装を根本的に考え直さなければならず、猛勉強ののち、あめ菓子や薬品の包装に使われていた赤いセロハンの裁ちくずに目を付けた。細長い切れ端を筒状の袋になるようにノリづけし、中身を詰め込んだ。試行錯誤の末、衛生的で保存期間が長く、取り扱いに便利な「セロハンウインナー」が誕生。このとき、日本のハム・ソーセージ業界特有の「熟成」という方法の基礎が生み出された。神戸市内の飲食店、スタンド、バー、カフェで「セロ」の愛称で親しまれ「爆発的ヒット商品」になり、愛され続けるロングセラー「ポールウインナー」へと80年の歴史をつないでいる。
〝第二のふるさと神戸〟で再び
セロの人気で新工場を建設、従業員30人を雇うほどになったものの、戦況悪化に伴い、時代はハム・ソーセージづくりどころではなくなる。1945(昭和20)年6月5日、神戸の市街地は大空襲に見舞われ、伊藤氏自身も爆弾破片が太ももを貫通する重症を負ってしまう。伊丹、岐阜と疎開先を転々としながらも、六甲の山々を思い出し、たとえ焼け野原になっていようとも、もう一度神戸に行ってみたいと心は動いたという。「神戸は第二のふるさとになっていた」と当時を振り返る。
そして8月15日、終戦。「一刻も早く神戸に戻らなくてはならない」と心に決め、9月初め神戸に向かった伊藤氏が目にしたのは、無残なまでに変わり果てた街の姿だった。ぼう然と立ちつくすが「ハム・ソーセージを再び作りたい」という強い思いで立ち上がる。しかし十分な原料がない。ふとのぞいた長田区の中央市場で売れ残っているサメを見つけ、「これでいこう」と決める。熟成と脱臭に工夫を重ね、翌年、戦後第一号の魚肉ソーセージ「ニューソーセージ」が完成、4月7日から販売開始。味の評判も良く、3カ月後には灘区備後町に新工場を構えることになる。少しずつ畜肉原料も出まわり始め、それまでの経験を生かし質の高い寄せハム製造技術の開発に成功する。昭和20年代後半には売り上げもハイペースで伸び、備後町の本社工場を拡張し、その勢いは周辺が〝伊藤町〟と呼ばれるほどだったという。
このころ、「自分の会社だけがいくらいい製品を出しても、業界全体が歩調をそろえなければ製品全体のイメージダウンにもなり、お客様のためにならない」と考え、最も重要な温度管理、製造工程を業界全体に公開している。この伊藤氏の度量が、日本の代表的なハム・ソーセージ製品「プレスハム」を生み出すきっかけとなった。
神戸で合格すれば大丈夫!
やがて、ハム・ソーセージ業界の戦国時代がやってくる。他業種からも激しい攻撃を受け〝ハム男〟のど根性が燃え、新工場建設を決意。候補地誘致合戦の中、現在本社を置く西宮を選んだ。そこには「神戸から遠くへ離れたくない」という強い思いがあった。その後、東京の目黒工場の新設を足がかりに市場を広げ〝全国ブランド伊藤ハム〟へと発展を続けていく。
30年以上前、伊藤氏は「技術がいくら進歩しても原料そのものが悪いと、もちろんいい味の食べ物はできない。ところが最近、残念なことにその原料の品質が低下してきた。牛肉、豚肉、魚肉、鶏肉、鶏卵、果実、野菜すべてしかり」と、今の日本の食事情を予言するかのような警鐘を鳴らしている。「味覚で勝負するか価格でいくか、正直なところ迷うこともある」としながらも、「私はやはり真の味覚を追求するのが本道で、それが品質の向上につながると信じる。その点、神戸で〝テスト〟に合格すれば、どこへ持って行ってもまず大丈夫と言えると思う」と締めくくっている。神戸はこの期待に応えるべく、味覚と品質への確かな目を持つ街であり続ける責任があるといえるだろう。
参考文献
伊藤傳三『続け根性』サンケイ新聞社出版局、
昭和46年1月5日初版発行

ロングセラー「ポール・ウインナー」の元祖である「セロハンウインナー」は、1934年に灘区大和工場で誕生