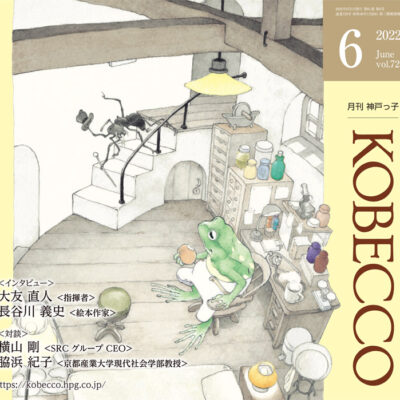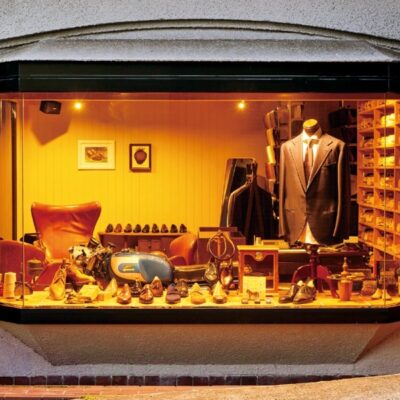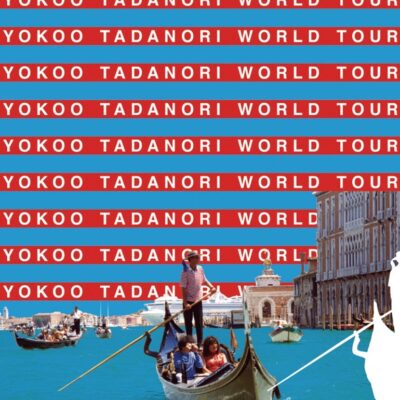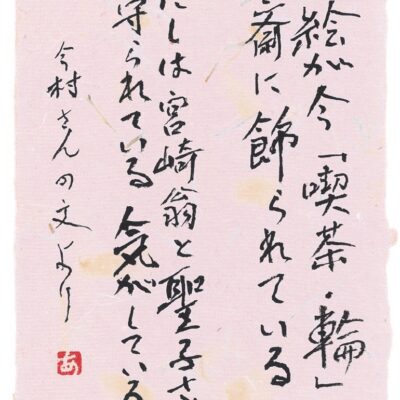6月号

ノースウッズに魅せられて Vol. 35
いのち巡る水
どんよりとした厚い雲から、絶え間なく降りしきる雨。森の木々の葉が受け止めた雨粒は、幹を伝って地面へと注いでゆく。カサカサに乾いていたコケもたっぷりと水分を含んでスポンジのように柔らかくなった。湖岸の岩が濡れると、より重厚なトーンへと色彩が引き締まる。
そうして地面に届いた雨は、ゆっくりと時間をかけて硬い岩盤の隙間に染み込んでゆく。やがて、地中に蓄えられた水は、どこからか湧き出して、湖を満たすのである。
長い野営の間、炊事に使う水は、そんなふうに空からもたらされ、森と大地を巡ってきた水だ。毎日毎日、目の前に広がる湖岸に行ってはキャンプ用のポットで水を汲む。そのまま飲む時もあれば、食事を通して湖の水を体内に取り込む。人間の体の半分以上は水でできている。いつかは僕の中を流れる水が、すべてこの湖の水に置き換わる時が来るはずだ。一週間、二週間と日が経つにつれ、自分と湖とが少しずつ一体化していくような気がしてくる。
森でひとり雨に打たれていると、肩や頭に打ちつける雨音の騒がしさに反比例するように、気分はとても静かで落ち着いてくる。都市の暮らしで硬く乾いた心がうるおいを取り戻し、溜まった埃を洗い流してくれるからかもしれない。カリブーもクロクマもオオカミも、この雨の日に、どこでどんなふうに過ごしているのだろう。一年のうちに一日でいいから雨に打たれる日があっても良いと思う。その方が、動物の仲間としての人間の、あるべき姿を思い出させてくれるから。


写真家 大竹英洋 (神戸市在住)
1975年生まれ。一橋大学社会学部卒業。撮影20年の集大成となる写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』で第40回土門拳賞受賞。写真家になった経緯とノースウッズへの初めての旅を描き、第7回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞したノンフィクション旅エッセイ『そして、ぼくは旅に出た。』が、2022年5月に文春文庫となって刊行された。