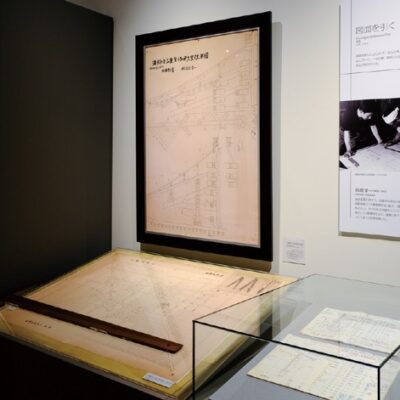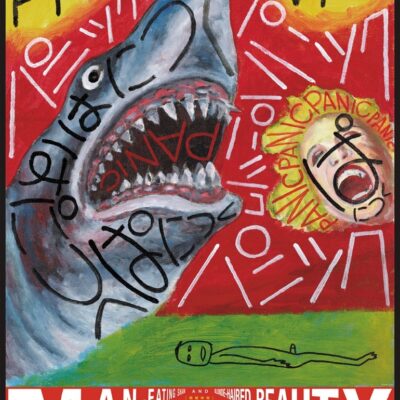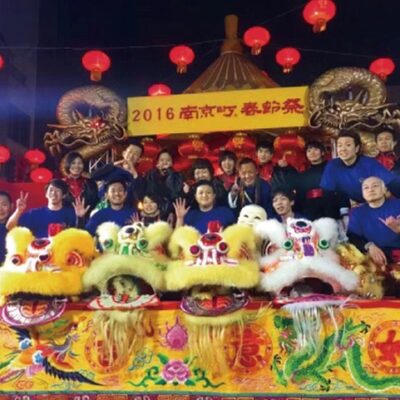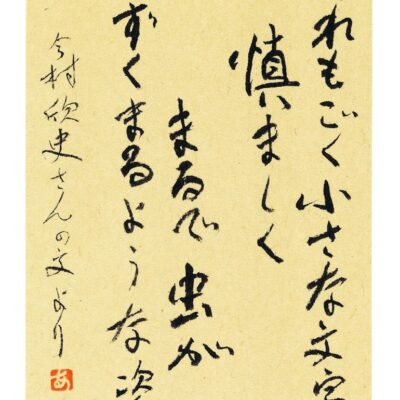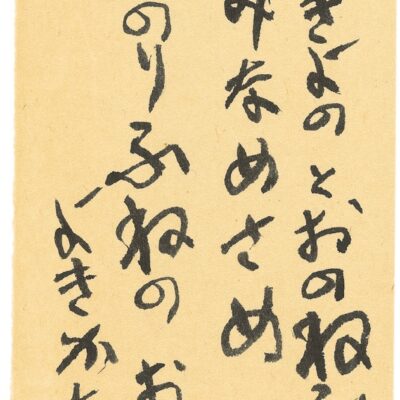1月号

映画をかんがえる | vol.22 | 井筒 和幸
振り返ってみると、1980年代は人々が欲望のままに虚栄を生きた時代だ。ボクも企業のコマーシャル映像を作る仕事もして忙しかった。「おいしい生活」なんていうデパートの宣伝コピーに煽られたか、人々は金を稼げるだけ稼ぎ、贅沢に憧れ、見栄を張って生きていたように思う。東京の地下鉄車内ではアルマーニのスーツをだらしなく着た若者が漫画週刊誌を読んでいた。通りでは赤い口紅の女子大生がロレックスの時計をしてBMWを走らせていた。誰が裕福なのか見分けがつかず、人々はつましい現実を嫌い、もがいていた。何年か後に経済が破綻するとは予想していなかった。ボクは何が「おいしい生活」か分からなかった。東京に親友はいなかったし、都会の世知辛さにため息をつき、息が詰まると郷里の奈良に逃げ帰った。生きる糧になった映画は思い出せない。社会を撃つ問題作もなかった。郷里で田園風景を眺めて、自分はどんな映画を作ればいいのかと悩んでいた。
「トワイライトゾーン/超次元の体験」(84年)というオムニバス映画があった。スピルバーグ製作と聞くだけで調子の良すぎる話は嫌だったが、これは理由があって観た。第一話に登場するビック・モローに逢いたかったからだ。少年の頃に夢中で見た超人気戦争ドラマシリーズの「コンバット!」で、サンダース軍曹役で世界中に名を馳せたのが彼だ。サンダースは戦場でいつも冷静な判断を下してナチスと戦い、同時に、正義と邪悪の先にある戦争の虚無さえも毎週、教えてくれたのだ。その彼がこの一話の撮影事故で命を落とし、これが遺作になってしまったのだ。「軍曹、色々と教えてくれてありがとう」と、この未完成っぽいホラー映画に、軍曹の顔をダブらせながら追悼したのを覚えている。
84年の初春、ボクは徹夜続きの撮影に追われていた。角川映画から頼まれた「晴れ、ときどき殺人」(84年)というアイドルものだ。「晴れた日でも殺人は起こるという話だし、好きに撮ってよ」とプロデューサーが励ましてくれた。自分の作りたいものではないけれど、映画とは何ぞやと考える機会でもあったし、脚本家が上げたシナリオに現場で即興ギャグを足し、思いつくまま撮った。
この映画の目指すものは何か?と製作者に訊くと、「アイドルファンがアイドルに惚れ直すように料理してくれたら。でも、書店に並ぶ原作本で犯人は誰かはバレてるし、映画では一捻りしてほしいけど」と返された。まあいいや、大いに名を売ってやれとボクも腹を括った。ミステリーに興味は元から無いし、せめて芝居ができる芸達者を探した。先輩のキャスティング担当者が「演劇調の俳優や、悪人役だと意識して演じる奴はダイコンだし外すから」と助けてくれた。久しぶりに聞く名言だ。顔を白塗りして舞台に立つ役立たずという意味だ。そうか、リアリズムなんてこのお伽話には要らないかと思うと、肩の力が抜けて楽になった。浅香光代さんに伊武雅刀、九十九一、中でも名司会者の前田武彦さんは頼もしかった。実は戦時中、郷里の母の実家近くにあった航空隊に予科練習生として赴任し、勤労女学生だった母を覚えてると話してくれた。現場でも前田さんには戦争話を聞いてばかりで、「戦争の真実を撮って下さいな」と言われたのを思い出す。
自作は5月末に封切られ、新宿の映画館の舞台挨拶はワイドショーの生中継まで入り、ボクはため息ばかりついていた。翌日、見逃していた「スカーフェイス」(84年)がかかる渋谷の映画館に身を沈めに行った。昔の「暗黒街の顔役」の舞台を現代のマイアミに変え、アル・パチーノがキューバ難民から麻薬密売王に成り上がり自滅するまでを演じた意欲作で、金に溺れて誰も信じなくなる孤独者の叙事詩で、気晴らしどころか、映画の醍醐味とはこれだった。
「ところで君の撮ったものはそれは映画か?一体、何だ?」とそのスクリーンから問い糺された気がして、落ち込んで帰ったのも覚えている。
人々が現実を忘れようと虚構に生きた時代だ。夏に公開された『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』は空前の大ヒットだった。
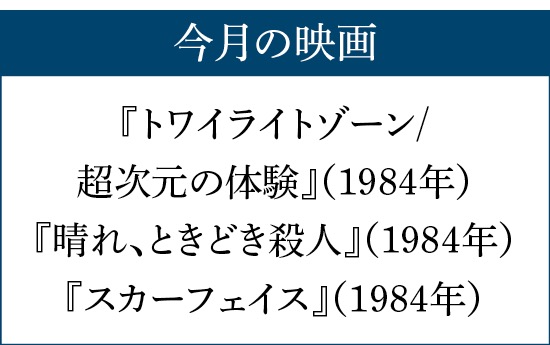

PROFILE
井筒 和幸
1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm映画『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD発売中。