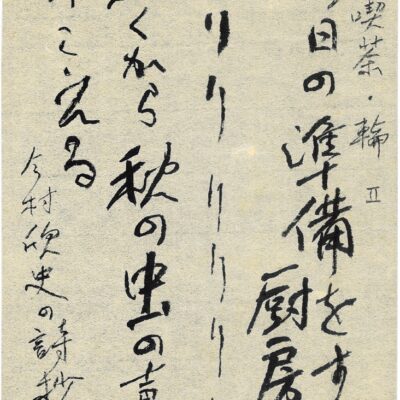3月号

ノースウッズに魅せられて Vol. 20
雪原をゆく
氷点下マイナス20度に下がった快晴の朝。すでに湖は厚い氷に覆われ、雪の積もった白い雪原と化している。こうなるともう水面にカヌーを浮かべて旅をすることはできない。今度はトボガンと呼ばれるソリの出番である。
地域によって形の細かな違いはあるが、トボガンもカヌーと同じようにノースウッズの先住民たちが伝統的に使ってきた移動の道具である。先端に丸みを持たせることで雪に沈み込むのを防ぎ、樹林帯でも取り回しが良いように幅が細くできている。冬の旅はそんなトボガンに野営の道具を乗せ、繋いだロープを自分で引いて歩いてゆくのである。
厳冬期のノースウッズはまるで砂漠だ。空気はカラカラに乾燥し、雪は砂つぶのようにサラサラと風に流されてゆく。水辺に集っていた水鳥たちも、美しい歌声を森に響かせていた小鳥たちも、ずいぶん前に南へと去ってしまった。耳をすまして聞こえてくるのは、雪原を渡る風と、トボガンが滑る音、そして自分の吐息ぐらいのもの。カヌーの季節には繰り返し湖岸の岩に打ちつけていた波の囁きが懐かしい。
ワックスを底面に塗っておいたトボガンは平坦な湖面を軽快に滑ってゆくが、粉雪に沈まないように履いたスノーシューを一歩一歩持ち上げながら進んでいるので、体がすぐに暖かくなってくる。しかし、汗をかいてしまってはまずい。肌についた水分が急激に体温を奪って凍えてしまうのだ。
上着を一枚脱ごうと立ち止まると、ドクドクと心臓が動いているのがわかる。生命の存在を拒むかのようなこの極寒の世界で、脈打つ鼓動を胸の奥に感じる時ほど、自分が生きていることを実感することはない。

写真家 大竹英洋 (神戸市在住)
北米の湖水地方「ノースウッズ」をフィールドに、人と自然とのつながりを撮影。主な写真絵本に『ノースウッズの森で』(福音館書店)。『そして、ぼくは旅に出た。』(あすなろ書房)で梅棹忠夫山と探検文学賞受賞。2020年2月、これまでの撮影20年の集大成となる写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』(クレヴィス)を刊行した。