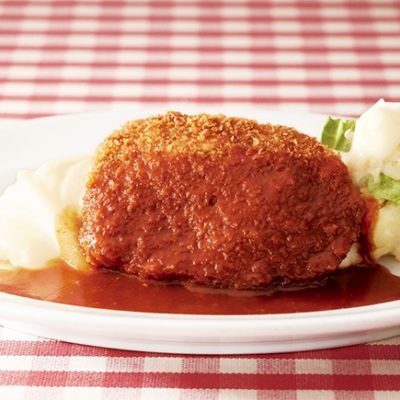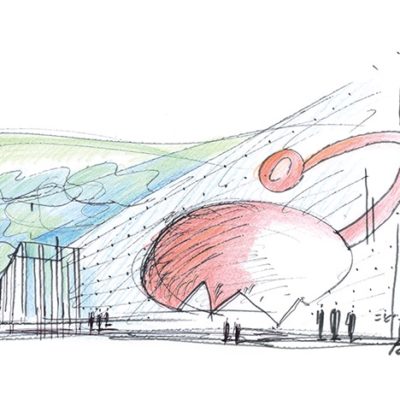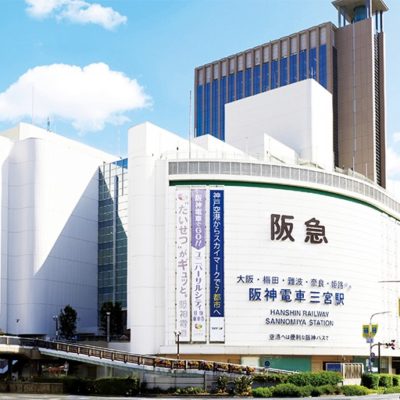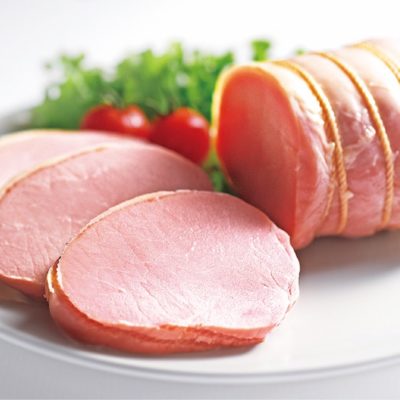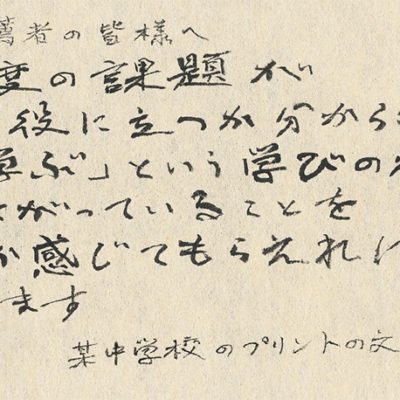11月号

ノースウッズに魅せられて Vol.04
動物界の建築家
秋も深まってくると、森の動物たちは、冬ごもりの準備に忙しい。なかでも熱心なのがビーバーたち。
彼らは冬眠をせず、自分たちで蓄えた木の枝を食べて、約半年にも及ぶ、暗く寒い冬を生き抜く。
家族全員の越冬には大量の枝が必要で、水深を保つダムの補修や、ロッジと呼ばれる巣の手入れにも忙しい。
彼らの勤勉な性質はよく知られ、英語で「work like a beaver」といえば「せっせと働く」という慣用句だ。
今でこそ、ノースウッズのいたる所で見られるビーバーだが、実は長い受難の時代があった。それは17世紀から19世紀まで北米で栄えた、毛皮交易の時代である。
当時のヨーロッパ貴族の間では、ビーバーの毛皮から作られたフェルトを用いた帽子が大流行。服飾の中でも帽子は富と権力の象徴であり、大枚をはたいて新調したビーバー・ハットは社交界での自慢だった。
ヨーロッパでは16世紀までにほぼ絶滅したビーバーだが、需要の高まりに押され、北アメリカ大陸にもフランスとイギリスから毛皮商人が押し寄せるようになった。
湖水をカヌーでつなぐ交易網が発達。多くの交易所が設置され、先住民が持ち込んだ大量の毛皮が、ヨーロッパからの鉄器、毛布、ビーズ、タバコ等と交換された。
やがて帽子の流行は廃れ、ビーバーの乱獲は終わったが、交易所はその後、現在のカナダに存在する町や都市へと発展していったのである。
歴史を紐解けば、枝を運んでロッジやダムを建設し、せっせと働いているうちに、いつしかビーバーはカナダ近代国家の礎まで築いていたと言えるのかもしれない。
2020年5月に新たに公開しました


写真家 大竹 英洋
北米の湖水地方「ノースウッズ」をフィールドに、野生動物や人と自然との関わりを撮影。主な写真絵本に『ノースウッズの森で』(福音館書店)。『そして、ぼくは旅に出た。』(あすなろ書房)で梅棹忠夫山と探検文学賞、2018年日経ナショナルジオグラフィック写真賞最優秀賞受賞。