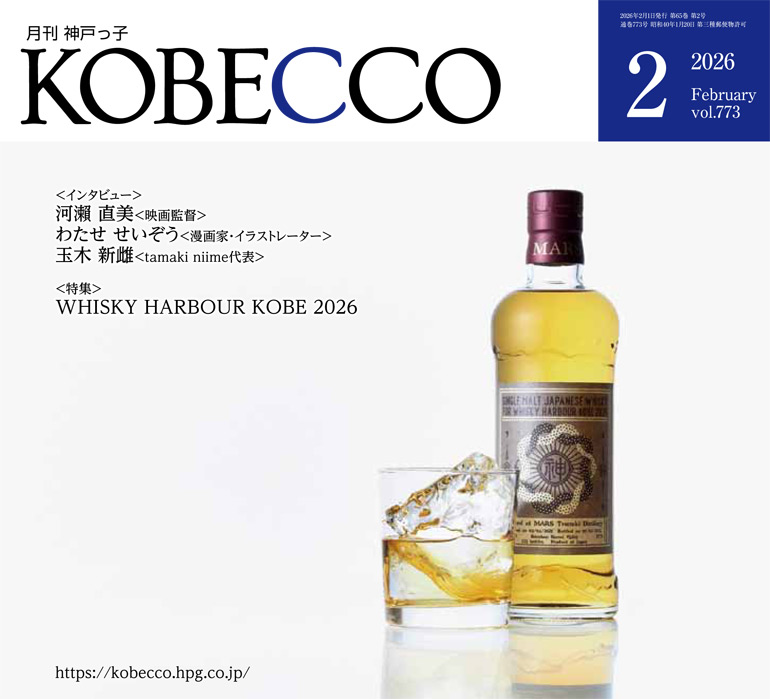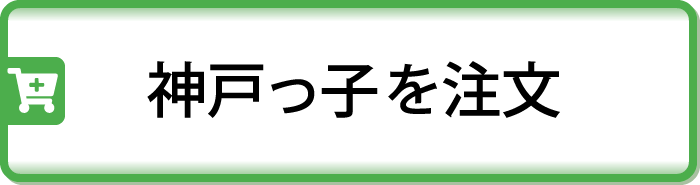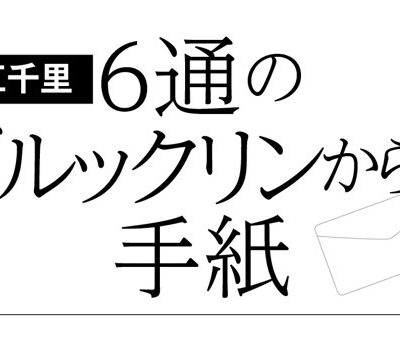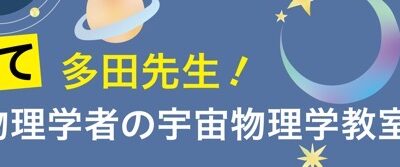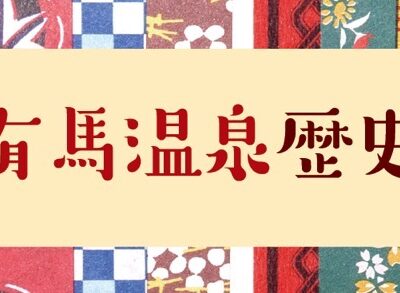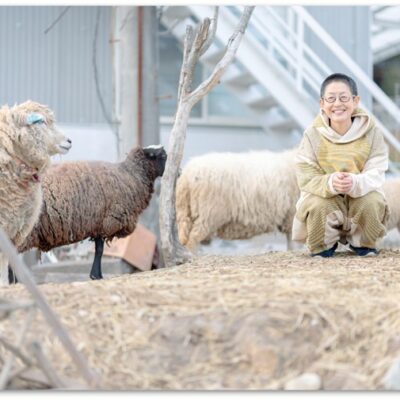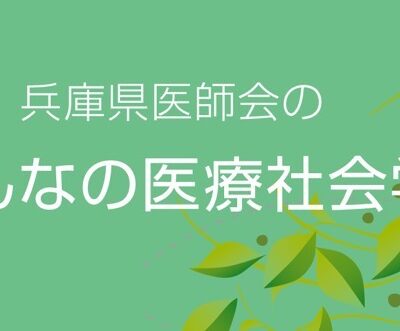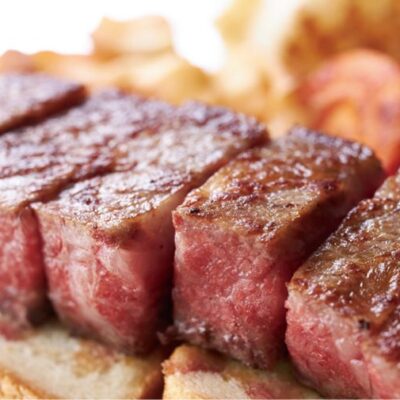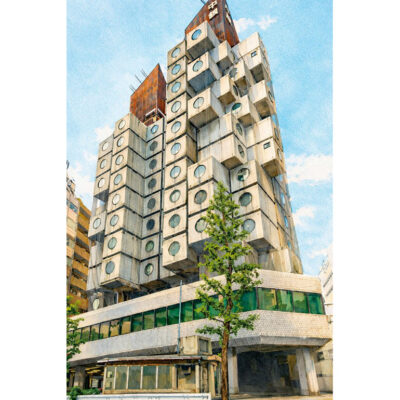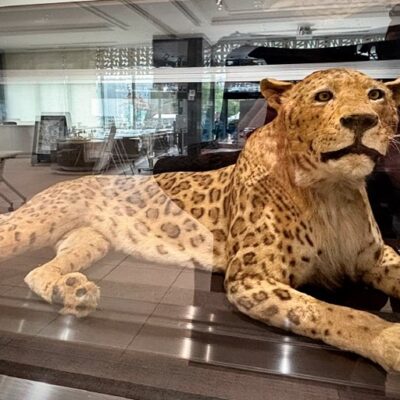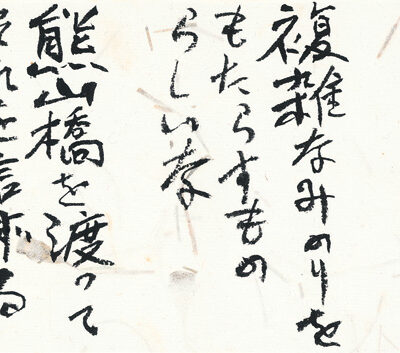3月号

流通科学大学で阪神・淡路大震災30年シンポジウムを開催|社会インフラとしての流通─ 30年を振り返り、未来を創造する
1月11日、流通科学大学でシンポジウム〝「阪神・淡路大震災30年」届けるって、やっぱり流通だね。水、ガス、電気、食品、そして人を想う心も!〟が開催され、100名以上が集った。
最初に清水信年学長があいさつ。想定外な事態が起こる災害時に流通は何ができるかを議論し今後に繋げていただければと語り、その後、全員で震災の犠牲者に黙祷を捧げた。
続いてローソン専務執行役員の郷内正勝氏が登壇、「【阪神・淡路大震災から30年】ローソンの災害対応について」と題する基調講演が。当時、尼崎~明石の約半数の店舗が営業できない状況になったが、東京から応援隊を派遣し翌日には約7割を再開、ローソンの看板の灯りが多くの人に勇気を与えたことから「看板に明かりを灯すことの大切さ」を感じたと振り返った。また、東日本大震災では従業員が店に戻って津波の犠牲になり「最も大切な命を守るため避難することの重要性を身をもって学んだ」と郷内氏。能登半島地震の対応も検証して、現在は安否確認システムや災害時のマニュアル、通信環境などの整備、自治体やインフラ企業との連携、防災訓練などの取り組みをおこなっていると紹介し、「平時も災害時も身近で必要な存在となり、共助社会の実現に貢献し続けていく」と決意を新たにした。
さらにパネルディスカッション「社会インフラとしての流通─30年を振り返り、これからを展望する」が流通科学大学の白鳥和生教授の司会のもと、ダイエー社長の西峠泰男氏、基調講演をおこなった郷内氏、前神戸市消防局長で神戸市緑化協会理事長の鍵本敦氏、流通科学大学を運営する中内学園の中内潤理事長をパネリストにおこなわれた。当時ダイエー副社長として陣頭指揮を執った中内理事長は、道路や港湾の情報が取得できず流通ルートをどうつくるかが大きな問題になったと回顧する一方で、長田消防署員として救助の最前線に立っていた鍵本氏は3日間寝ずに火災現場を駆け巡ったが食料や物資の調達に困り、応援車両が来ても燃料がなく活動が停滞したと当時のリアルを語ると、白鳥教授は改めて流通の重要性を指摘。西峠氏は、大規模店舗は避難場所や通信の拠点としての機能も担い、必要な物資を滞りなく供給するだけでなくまちづくりの再建の起点となる役割があることを震災で実感したと述べた。
その上で今後どうあるべきかについて議論され、何が重要かという問いに対し中内理事長は被災状況やエリアによるニーズの変化への対応、西峠氏は日頃からの信頼関係やネットワークの構築を挙げた。郷内氏は被災地の流通を支えているのは被災者なので、被災地外の人がその負担軽減を考えるべきと語り、鍵本氏は地震の活動期に入った日本に住んでいる以上、一人ひとりが災害を「自分事」として考えるべきだと訴えた。
その後質疑応答があり、最後に白鳥教授が「買いたい物を買いたいときに買える流通もライフラインである」という流通科学大学の創設者でダイエー創業者の故・中内㓛氏の言葉を紹介しつつ、過去の教訓を生かして「未来は創造できる」と締めた。

流通科学大学の白鳥和生教授が司会を務めた

右より、中内学園の中内潤理事長、前神戸市消防局長の鍵本敦氏、ローソン専務執行役員の郷内正勝氏、ダイエー社長の西峠泰男氏