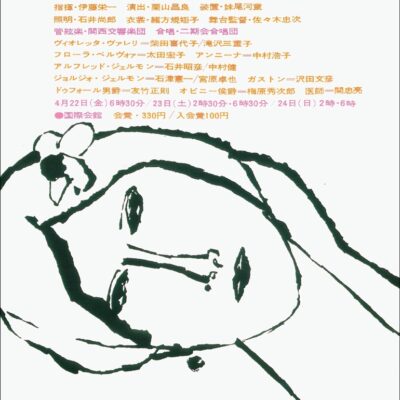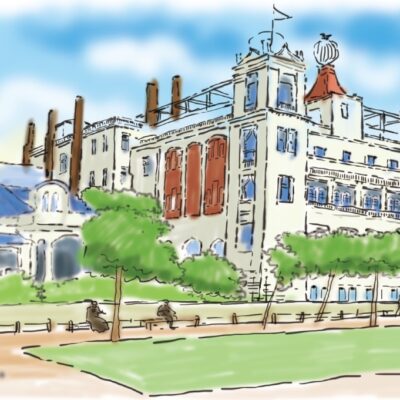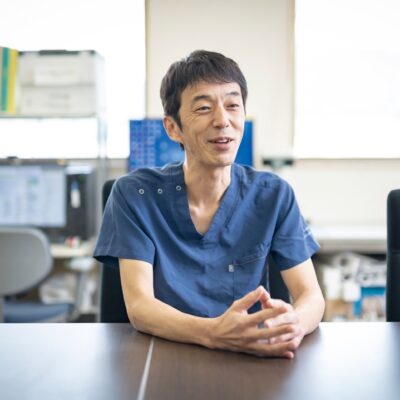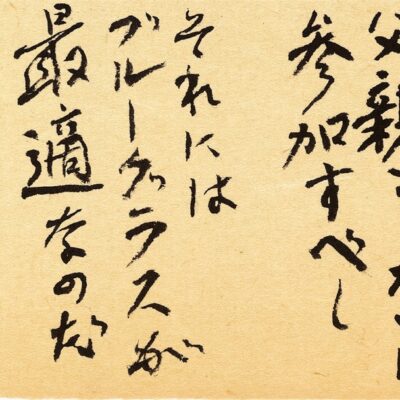10月号
神戸偉人伝外伝 ~知られざる偉業~(54)後編 井上靖
独自の文学概念、柔道哲学…
時と国境を超えた世界観
普遍の世界観
1949年、「文学界」(12月号)で発表され、翌1950年に芥川賞を受賞する「闘牛」よりも先に「文学界」(10月号)で発表された「猟銃」も、井上靖が毎日新聞大阪本社学芸部の記者時代に執筆した短編小説だ。
「闘牛」が西宮球場を舞台にしているように、「猟銃」も神戸市内や西宮市の夙川駅、芦屋市など当時、彼が暮らしていた地元周辺が舞台。戦後の〝阪神間モダニズム〟の世界観が作品の根底に流れている。
これまで、「猟銃」は何度もテレビドラマ化や映画化、舞台化され、その度に話題を集めてきた。実は井上が初めて発表した小説がこの「猟銃」だった。
物語は「私」が寄稿した一篇の詩から始まる。その詩には私が出会った見知らぬ一人の猟人のことを書いたのだが、「それはおそらく自分のことだ」と三杉穣介という人物から突然、手紙が私の元へ届く…。
1961年、松竹で五所平之助監督により初めて映画化された。佐分利信が三杉役を、三杉の妻を岡田茉莉子、三杉の不倫相手を山本富士子という当時のスター俳優がキャスティングされ話題を呼んだ。
1963年には後に国会議員となる元宝塚歌劇団の女優、扇千景と、銀幕のスター、佐田啓二が共演してテレビドラマ化された。佐田は中井貴一の父としても知られる。
2003年には大竹しのぶ、松重豊共演で映画界の重鎮、行定勲監督が演出しドラマ化されるなど、井上の描く世界観は世代を超えて親しまれてきた。
さらに、2011年には中谷美紀が一人三役に挑んだ舞台公演が日本、カナダで行われるなど〝阪神間モダニズム〟に込めた井上の世界観は国境も超え、人々を魅了してきた。
実は、井上がノーベル文学賞の候補に幾度となくノミネートされていたことも、後に明らかになっている。
才能が結集
井上が毎日新聞大阪本社の編集局にいたころのこんな〝秘話〟を元毎日新聞記者が教えてくれたことがある。
後に〝漫画の神様〟と呼ばれる手塚治虫は、現在の大阪大学に通う現役医学生としてプロの漫画家としてデビューした。
そのデビュー作「マァチャンの日記帳」は1946年、毎日新聞の小学生版で連載された。まだ、大学生だった手塚は完成させた漫画の原稿を抱えて毎日新聞大阪本社の編集局を訪れていた。
新聞社の編集局は一日中、締め切りに追われ、慌ただしく記者や整理部員たちがせわしなくうごめいている。
まだ10代だった手塚はいつもその雰囲気に圧倒されながら編集局を訪ねていたと想像される。だから、手塚は知人らに、こんな話をしていたと言う。
「大阪の編集局に行くと学芸部のデスク(副部長)の隣に、いつも怖い顔をした女性記者がいる」と。
手塚がそう語っていた女性記者とは、後に作家となる山崎豊子のことだ。そしてそばにいたデスク(副部長)とは井上靖のことだ。
昭和の同じ時代に、後に有名作家となる新聞記者の井上と山崎、そして後に漫画の神様と呼ばれる医学生の手塚が同じ場所で出会っていたことに不思議な運命を感じないわけにはいかない。
柔道家の顔
幼いころから文学に親しみ、新聞記者を経て作家となった井上。〝物静かな佇まいの文化人〟というイメージが根強いが、実は屈強な柔道家としても知られている。
神戸出身で講道館柔道の生みの親、嘉納治五郎をこの連載でも紹介したが、講道館と一線を画する柔道に井上は青春を懸けていた。
金沢市の通称〝四校〟と呼ばれた旧制第四高等学校(現金沢大学)時代。高専柔道(後に七帝柔道)と呼ばれた寝技、締め技中心の柔道に井上は魅了された。
井上の自伝小説「北の海」には、井上が高専柔道に明け暮れた青春時代が綴られている。
なぜ、井上は高専柔道にのめりこむことになったのか。
静岡高校の受験に失敗し、「怠惰な生活を送っていた」井上は四高柔道部員と出会い、初めて高専柔道を知る。
それは、「練習量がすべてを決定する柔道」だった。自分が取り組んでいた柔道との違いに驚愕、感動した井上は高専柔道の修行のために金沢へ向かった…。
世界中に普及させるために、嘉納は危険な技が多かった柔術を安全なルールへと変え、講道館を創設した。その結果、講道館柔道は五輪競技として採用され、今も世界各国で人気の格闘技として定着した。
一方、井上がのめり込んだ高専柔道は、柔術の流れを残す殺人技を残した柔道だった。
試合では一本背負いなど派手な大技が決まることは少なく、寝技や締め技で勝敗が決するのも高専柔道の特長だ。
大宅壮一ノンフィクション賞受賞作「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で知られる作家、増田俊也は「北の海」を読み、高専柔道に憧れ、愛知県の高校から北海道大学へと進学した。「北の海」に感化されて柔道を始めたという者は少なくない。
井上が撒いた〝種〟は、今もさまざまな分野で芽吹いている。
=終わり。次回は小泉八雲。
(戸津井康之)