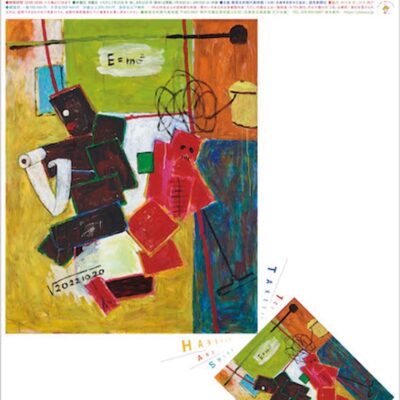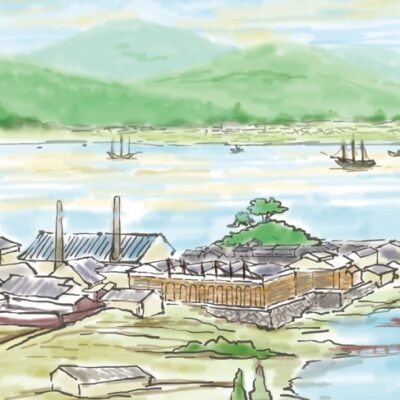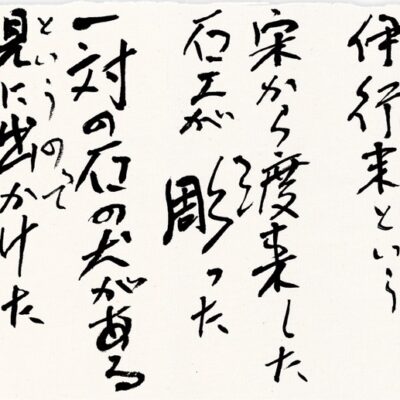6月号

⊘ 物語が始まる ⊘THE STORY BEGINS – vol.43 落語家 立川 談春さん
新作の小説や映画に新譜…。これら創作物が、漫然とこの世に生まれることはない。いずれも創作者たちが大切に温め蓄えてきたアイデアや知識を駆使し、紡ぎ出された想像力の結晶だ。「新たな物語が始まる瞬間を見てみたい」。そんな好奇心の赴くままに創作秘話を聞きにゆこう。第43回は、1984年に落語の世界へ飛び込み、2024年の今年、芸歴40周年を迎えた落語家、立川談春さん。
文・戸津井 康之
「これから」に込めた意味…
40年修行してなお目指す新境地
独演会を貫く
今年1月から新境地で挑み続けている独演会がある。
「実は35周年の年…。次の40周年では何をしようか?そう、ずっと考えてきたんですよ」
こう話すと静かに立川談春は笑みを浮かべた。
熟考し、導き出したその答えは、「10カ月連続で、東京と大阪の会場でそれぞれ独演会を毎月一回ずつ開催する」というかつてない試みだった。
タイトルに付けた「これから」の意味を問うと「毎回、私の古典落語の十八番の演目を選んでいますが、同じ内容であっても、これまでとは違う。だって、35周年からでもすでに5年も経っているのですからね。観客に前に見たのと同じじゃないか。そう思われたら40周年として演じる意味がないですよね。十八番ですが、まだ、それが自分にとって最高の落語であるとは思っていません」
40年間、高座に上がり続けてきても、まだ、「これが自分の十八番だ」とは満足していないのだ。
だから、「まだまだ、これから…」と己を叱咤し、鼓舞する言葉を、あえて40周年の独演会のテーマに掲げたのだという。
挑む相手は観客か、それとも世間か…。いや、自分と戦い続けようと葛藤し、これまで以上に成長しようともがく落語家の凄みを取材中、何度も感じた。
一回の独演会で2つ以上(3つのときも)の演目を披露する。それを東京・有楽町朝日ホールと、大阪・森ノ宮ピロティホールで2回。これを10カ月連続で…。
現在は中盤戦。10月までのロングランの独演会の真っ最中だ。
いったい古典落語の演目を、いくつ覚えているのだろうか。
「古典落語の演目の数は計500ほどあるといわれています。その中で300ほどは覚えました。そのうち持ちネタとしては80ほどあります」
すぐにでも披露できる持ちネタだ。聞けば、師匠の立川談志から、「できるだけ多くのネタを持つように教え込まれた」と言う。
覚悟の入門
今から40年前、17歳で立川談志の元へ入門した。退路を断つ覚悟で、親の反対を押し切り、高校は中退した。
「10代、20代の修行?厳しかったですよ」と包み隠さず打ち明け、「その経験があるからこそ、40周年の独演会を続けている落語家としての今があるのだと思います」としみじみと語る。
落語界を牽引しながら一方で、俳優として数々のテレビドラマや映画にも出演してきた。
長らく落語会のスーパースターとして君臨してきた師匠の談志が今から13年前。2011年に亡くなって以来、落語以外のメディアへの露出を意識してきたと言う。
「30年か、50年か…。談志師匠は落語界全体の寿命を延ばしてくれた。自分は何年、それを延ばすことができるだろうか」と。
そのための〝武器の一つ〟が俳優活動だった。
それを実感する大きな転機は、師匠の死から3年後の2014年に訪れた。毎週日曜午後9時。かつてのお茶の間の人気ドラマ「東芝日曜劇場」の枠でこの年に放送された『ルーズヴェルト・ゲーム』(TBS系)への出演だったと振り返る。
演出を担当していたのは、昨年、社会現象ともなった人気連続ドラマ『VIVANT』の福澤克雄監督。
「今回は悪役だったから、次のドラマでは良い人の役でお願いしますね…」。そう依頼されたドラマが、翌2015年に放送され、これも大ヒットした『下町ロケット』だった。
「日曜に放送され、視聴率が判明する月曜日にテレビ局から花束が贈られてくるんですよ。15%を超えるとですが…」と、笑みを浮かべながら映像の世界で知ったルールを教えてくれた。
改めてテレビの影響力の大きさを実感したという。
「放送された次の日に、街を歩いていたら、知らない人が声をかけてくれるのですから」
俳優界にはいない独特の存在感を放つ役者を映画界も放ってはおかない。
先月、封切られた人気ドラマの劇場版である『映画 マイホームヒーロー』(青山貴洋監督)の出演も話題を呼んだ。
娘を守るため、暴力を振るう娘の彼氏を殺害するサラリーマンを演じた佐々木蔵之介と対峙する刑事を演じた。
「『下町ロケット』の撮影現場でAD(アシスタントディレクター)だった青山監督から出演を依頼されたんです」
「自分の映画監督デビュー作には絶対に談春さんに出てほしい」と直々に請われての出演だった。
この映画公開前に主人公を演じた佐々木さんを取材したとき。
「談春さんの刑事役が本当に凄かった。この映画のキーとなる重要な役で難しかったはず」と興奮気味に話す姿が強く印象に残った。
新人監督から重鎮俳優までが、現場で頼りにする、今や映画やドラマにとって欠かせない懐刀のような俳優の一人だ。
落語界の未来
大阪の天満天神繁盛亭、神戸の喜楽館など落語の定席が相次いで創設されるなど、「近年かつてない落語の盛り上がり、人気を感じますね」と向けると、「これまで、落語の歴史を振り返ってみても、その人気が沸点に達したことはないんですよ」とやんわりと、だが、毅然と否定された。
一方で、「過去400年にわたって落語の種火が消えたこともありません。落語には、人間にとって普遍的なものが込められているからだと思います」と続けた。
この、「火種は絶対に消さない」という覚悟で、全国各地の高座へ上がり続けた結果、「チケットが最も手に入らない落語家」と言われてきた。
この言葉の由来を聞くと「実は新聞の取材のときに私が自分でそう言ったからですよ。今思えば恥ずかしいですが…」と笑うが、実際、数千人を収容できる日本各地の大会場を満員にしてきた実績がこの言葉を証明する。
この日、取材した場所は大阪市内の大阪フェスティバルホールが入ったビルの一室。
現在建つ新しいビルへ建て替わる前の旧大阪フェスティバルホールで2008年、同ホール史上初となる落語家の独演会が開催された。旧館が閉館する直前のファイナルイベントで、落語家として最初で最後の独演会に挑んだのが立川談春、その人だった。
きっかけを聞くと、一人のシンガー・ソングライターの名を上げた。「実はさだまさしさんに、一度、このホールで落語をやるべきだ、と言われたんです。このホールで拍手を浴びてほしいと。他とは違うから。そう強く言われて」
さだの落語好きは有名で、そのさだから熱心に勧められたのだ。
同ホール閉館間際の〝ラストチャンス〟にそれが巡ってきたのだった。
さだから言われた言葉の意味とは?
「拍手が天上から振ってくるんですよ。あんな拍手は聞いたことがなかった。初めての経験でした」
俳優として、映画やドラマの撮影現場に立つとき。「一つの映画やドラマで、これだけ多くのスタッフや共演者が動いてくれている。俳優としてこの場に立つ自分の責任は重い。いつもそうプレッシャーを感じています」
片や、落語の独演会はたった一人で高座へ上がる。
大勢の観客を一人で笑わせたり、泣かせたり…。そのプレッシャーたるや想像を絶するのだが、「すべては自分一人の責任。失敗も成功も…。その日の高座に賛否両論があっても当たり前。もう慣れていますよ」
主戦場では、どんなプレッシャーにも動じない。言葉には出さないが、そんな矜持を感じさせる。日々弛まぬ努力を40年間、ずっと続けてきたからこそ語れる言葉だろう。さらに、続けた言葉に身が震えた。
「古典落語はずっと同じ内容。でも世の中は絶えず変化している。20年前と今では価値観も違う。今は経済、つまりお金が大事。そんな時代ですが、かつてはお金よりももっと大事なものがあったのです。観客が同じ落語を聞いてどう受け止めるのか?賛否両論あって当たり前…」。その言葉の裏には、いくら時代が変わろうと、人の心が変わろうと、師匠から受け継いだ伝統を背負い、弟子へと引き継ぐだけ。ぶれない覚悟で…。
40周年の次の構想はと問うと「45周年、50周年。その後もずっと…。一生、落語を続けていきたいですね」と謙虚に語る。
落語家となって40年。第一線に立ち落語会を牽引してきたが、まだ道の途上にいる。

撮影・服部プロセス

立川 談春(たてかわ だんしゅん)
1966年東京生まれ。1984年、立川談志に入門。1988年、22歳で二つ目に、1997年、真打ちに昇進。国立演芸場花形演芸会大賞を始め、数々の賞を受賞。古典落語の名手で、独特の話芸で魅せる斬新さが注目を浴び、「新世代の名人」と評される。今、最も旬な落語家の1人として、若い世代やクリエーターからの支持も厚い。
落語以外でもマルチな才能を発揮し、2008年には談志との家族以上の師弟関係や落語家前座生活を競った破天荒なエッセイ『赤めだか』を執筆、第24回講談社エッセイ賞を受賞する。演技力にも定評があり、連続ドラマ『下町ロケット』、映画『あいあい傘』、『七つの会議』、2023年にはNHK大河ドラマ『どうする家康』にも出演。2024年は、芸歴40周年を記念して有楽町朝日ホールと森ノ宮ピロティホールにて連続公演を開催中。